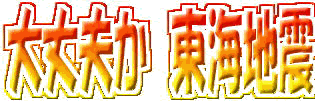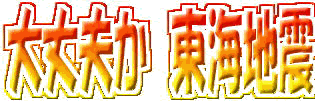■次 第
1.代表あいさつ(伊藤代表)
2.来賓あいさつ
愛知県住宅対策監山本氏
名古屋市住宅企画課長安藤氏
3.パネラー報告
パネラー:飛田氏、栗田氏、斎藤氏
4.ディスカッション
コーディネーター:井沢氏
|

伊藤代表あいさつ |
■パネラー報告の概要
(1)「東海地域を脅かす大地震のすがた」
名古屋大学工学部助教授 飛田 潤 氏
|
- 1970年代に出た「東海地震」は、その後のデータの蓄積によって、昨年からあわただしくなり、震源域が愛知県側に拡大され、地震防災対策強化地域も愛知県に広く指定された。
- 東海地震は、起こる前から起こること想定された地震。すなわち、予知することを前提として名前が付けられた地震で、警戒宣言が出される地震である。過去の発生時期と規模から推測すると2000年を過ぎた頃に起こってもおかしくない。
- 東海地震の愛知県の震度は5強から6強で、震度が6以上になると被害がひどくなる。
- 愛知県は、東海地震だけでなく、東南海地震の可能性も高く、南海地震とあわせて3つの地震が同時に発生する可能性があり脅威である。東海地震が大きくクローズアップされているが、実際は、三重県沖を震源とする東南海地震の方が、東海地方に対し大きな影響を与える可能性がある。
- 愛知県下には昭和56年以前に建設された耐震性の低い建物が非常に多く、特に名古屋市内が多い。耐震化は不可欠である。
- 地震を自分のこととして捉え、地震から守るべき一番大切なものは何かを考えていただきたい。
|
 |
(2)「阪神大震災の復興とまちづくり」
(株)アール・アイ・エー神戸支社長 斎藤 彰良氏
|
- 平成5年から神戸の再開発に関わるようになって、平成7年の阪神淡路大震災を契機に震災復興のまちづくりに携わるようになった。
- 災害時の教訓としては、家屋が倒壊して下敷きになった場合、人力では救出できないので、近所の助け合いや機材が必要であること。復興まちづくりを進めるためには、従前居住者が近くで住める応急住宅がないと、集まって議論ができない。被災して遠くに避難した場合は安否や所在を知らせる立札が効果的なことなどを学んだ。
- 復興のまちづくりでは、2段階都市計画が有効で、第1段階では基本的なことだけを早期に決め(六甲南では区域と1haの公園を決定)、第2段階で住民主導によるまちづくり計画を地元が行政に提案し、決定している。基本的な枠組みを早期に決めて、明示することが重要である。
- 六甲道駅南地区(5.9ha、第2種再開発)と舞子駅北地区の事例を交え、復興のまちづくりの取組みを写真を交えて紹介された。
- しかし本来的には、震災後復興ではなく、震災前復興として再開発事業に取り組むべきではないかと。
|
 |
(3)「専門家の緊急ネットワークづくり」
NPO法人レスキューストックヤード事務局長 栗田 暢之 氏
|
- 阪神淡路大震災の被災者支援活動に参加したのを契機に、全国の被災地での支援活動を推進し、愛知・名古屋水害ボランティア本部長に就任し、災害が起こる前の活動を支援するNPO法人を設立した経緯について説明。
- 阪神淡路大震災の際は、ボランティアを行う側も受ける側も慣れておらず、西宮市では、(過剰に集まった)救援物資を2300万円かけて償却処分した。
- 震災にあった方々からは、「まさか自分が」、「もうちょっと備えておけばよかった」ということをよく聞いた。阪神淡路大震災からの教訓として、家の倒壊による圧死、近所同士での助け合いが、まちづくりの原点であり、「家」と「コミュニティ」がキーワードではないか。
- 地域防災組織があっても活動はあまりされていないのが現状で、地域の防災意識を高めていくことが重要であり、東山学区での取組みを紹介された。
- 12/7に東山学区で、簡易耐震診断と家具転倒防止の地域ボランティア活動を予定しており、建築士などの専門家がヘッドになってアドバイスして欲しいと呼びかけられた。
- 今後は、簡易耐震診断、精密耐震診断、耐震補強工事へのプロセスづくりが課題と指摘された。
|
 |
■ディスカッションの概要
(出席者:パネラー3名、コーディネーター:井沢 知旦氏)
|

|
|
Q.地震予知はどのレベルまで可能か。
A.地震学的にはかなりの所までできると言われている
Q.2段階都市計画の基本的な考え方は何か。
A.行政的には、全体を復興させるのは無理で、拠点的なまちづくりを考える。それ以外はソフトな支援により、民間による取組みを加速させるのが狙い。
Q.名古屋市だけでも学区が200学区くらいあるが、市民の防災意識をどうやって高めていくのか。
A.小さな取組みがモデルとなって、少しづつ広めていくしかない。
Q.東海豪雨の復旧費960億円の1%でも事前に住民にばらまいておけば、大災害は防げたのではないか。
A.誰かが何かをやってくれるでは解決しない。自分として何ができるかを考えて欲しい。
Q.住民の防災意識を高めるための動機づけとして良い方法はないか。
A.被災地に記念碑をつくったが、被災者からはやめて欲しいとの声があった。忘れたいという気持ちはあるが、意識的にやらないと、世代が変わると忘れ去られてしまう。
Q.最後に一言
A.被災地での現場のことを伝えていくのが、我々のミッションであり、自分でやってみようと1人1人の意識を盛り上げていきたい。
A.震災前復興により、ハンデなしでの立ち上げを
A.正しい情報を的確に判断して欲しい。
|