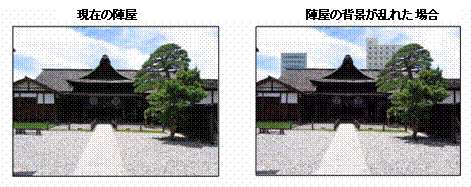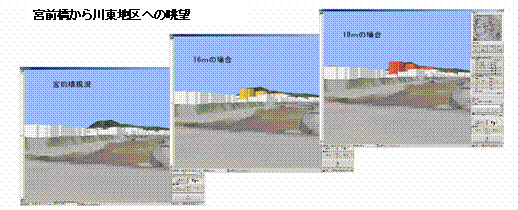|
2007年4月交流会
面積日本一 観光都市高山の景観づくりを学ぶ
〜高山市の景観計画策定の取り組みと実態〜
【日時】2007年4月19日(木)8:15〜18:00
【場所】岐阜県高山市
【参加者】20名(愛知まちコン会員) |
■行 程
8:15 名古屋駅太閤通口(旧メディアワン前)集合
8:30 名古屋駅西口出発(貸切バス)
11:00 高山市役所到着、市役所会議室にて市担当者からの説明
12:00 昼食(ひだホテルプラザ)
13:00 市内見学を兼ねて城山公園へ移動、城山公園後は市内自由見学
15:00 高山市役所駐車場集合、出発
18:00 名古屋駅前到着(自由解散)
|
1.高山市役所での説明会
景観計画などの説明をして頂いた高山市役所の方々
・高山市役所基盤整備部都市整備課 課長 武川 尚氏
・同上 主幹 小瀬克己氏
・同上 黒谷 渉氏
《高山市について》
- 高山市は平成17年の合併により面積が日本一となり、東京都と同程度の面積を有している。宮川を京都の鴨川に見立てた碁盤の目の町割りであり、小京都とも言われている。
- 江戸時代に天領として幕府直轄で治められたことで屋台町の基礎が築かれたが、明治から昭和にかけての鉄道の開通とともに旧商店街(現在の古い町並み)は衰退していった。
- 高山では商売をやめることを「しまいや」と言うが、商売をやめ、住宅として改築されたことで現在の古い町並みが残ってきた。
- 昭和30年代に大学の研究対象、映画のロケ地となるなど、外部から見られる機会が増えたことによって、住民が自ら町を守ろうとする機運が高まってきた。行政主導ではなく、住民主導でまちづくりを進めてきたことが高山市の特徴である。
|
| ☆市役所内での説明会の様子 |

|

|
|
《景観計画について》 - 「高山市潤いのあるまちづくり条例(各種の景観に関する取り組みを移行)」「新たな課題への対応(旧高山市街地の高さ制限、合併市町村の景観等)」を基本的な考え方として取り組んだ。
- 景観に対する意識の高い地区を対象に、素案段階で地域住民と意見交換会を開催し、合意形成に努めてきた。
-
地域の特性に応じた良好な景観形成を図る地域を景観重点区域とし、個別に規制・誘導基準を設けた。また、高山市にふさわしい色彩とするため、客観的な指標としてマンセル値を用いて色彩基準を明確にした。
- 高さ制限については、既存の建築物の実態調査とCG(コンピューター・グラフィックス)を利用した眺望点の検討を経て、所要の高さを決定した。
- 高山市の玄関口にふさわしい景観形成に向け、IC周辺の「新宮まちづくりの会」が自主的に屋外広告物の規制を進めている。この規制は、十数年前から既存の看板類の撤去などに取り組んできた結果であり、地域が自立・成熟するまでには時間と根気が必要である。
|
| ●CGでのシミュレーション(高山市景観計画資料) |
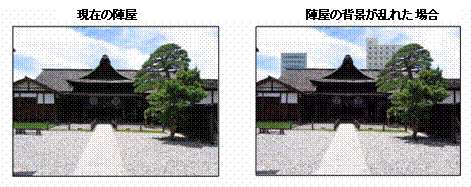
|
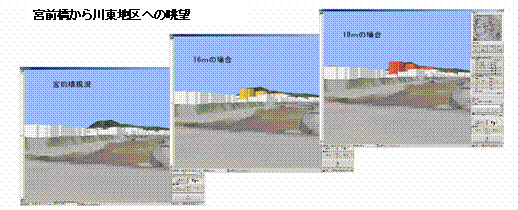 |
《今後に向けて》
- 建築物の高さ規制の担保を強化するため、都市計画における高度地区の指定も考えている。
- 景観重点地区を対象に屋外広告物の基準を強化しているが、今後は、全市的に屋外広告物の基準を設けて、規制・誘導を図りたいと考えている。
- 景観計画を策定すれば、景観形成を図れるということではなく、高度地区や地区計画等々の各種の手法を組み合わせながら、高山市としてベストな方法を選択していきたい。
|
《質疑・応答》
| Q: |
景観重要建造物で建築基準法の特例措置、消防法の特例は行われているか。また、景観重要建造物に対する助成等は行っているか。 |
| A: |
現時点では景観重要建造物の指定はなく、今後、他都市での取組みを参考にしながら検討していきたい。なお、古い町並みの区域では伝建地区としての補助の他、市条例により助成は行っている。
|
| Q: |
市民参加及び合意形成手法のプロセスを教えて頂きたい。 |
| A: |
素案段階で意見交換会を行った。
|
| Q: |
建物の修景に対するガイドラインなどはあるか。 |
| A: |
全域にわたるガイドラインは策定していないが、土地区画整理事業において個別にガイドラインを定めている地区はある。
|
| Q: |
高さ制限における合意形成段階で、反対意見などは無かったのか。また、反対に対してはどのように対応したのかを教えて頂きたい。 |
| A: |
高さ制限は、駅裏の高層マンションの建設を契機に考えるようになり、既存の建物の調査とCGによって理解を得るように努めたが、関係者全員の合意を得ることは困難であった。頂いた意見のなかには、市が提示した高さ基準の案よりも低くした方が良いとの意見もあり、将来の高山市のまちづくりを市民と共有していくことで、理解は得られると考えている。
|
| Q: |
景観計画を策定しようとした背景、及び策定組織があれば教えて頂きたい。 |
| A: |
景観法の施行と合併を契機として、旧市町村の景観を一体的に考える必要性が生じた。また、観光都市として、都市の色や景観を考えることが重要であると考えた。策定組織は、地域の代表、各種団体、専門家で構成される「まちづくり審議会」を設置した。
|
| Q: |
今後、世代交代が進むなかで、景観に関する意識の伝承についてはどう考えているか。 |
| A: |
高山市では、「屋台組」という祭りの地元組織がある。この組織を通じて、高山市独自の伝統や文化が親子代々伝承されており、景観についても伝承されていくものと考えている。また、高山市の景観を維持していくための柱は2本あると考えている。1つ目は、馬籠や妻籠などとは異なり、そこに生活の場があり、住み続けることで景観に関する意識も伝承されていく点である。2つ目は、古い町並みを維持するための技術の伝承であり、飛騨の匠と言われるように、お金ではなく誇りとしてその技術が伝承されていく点である。
|
|
2.市内見学
市内案内など今回の企画をサポートして頂いた国土交通省中部地方整備局高山国道事務所の方々
・高山国道事務所 副所長 田口雄二氏
・同上 調査課計画係長 大原千明氏
・同上 調査課専門調査員 尾崎俊彦氏
|
城山公園での説明の様子
|
市内の自由見学の様子 |
市内の自由見学の様子
|
市内の自由見学の様子
|
高山市役所前での集合写真 |
3.視察の感想
- 住民先行型でまちづくりが進められており、地域のコミュニティを感じた。
- 景観づくりを進める目的を「観光」というテーマに絞って取り組んでいることが、良く分かる景観計画の内容であった。
- 自主的に景観づくりに取り組む地域住民と、それを受け止めることができる行政が、良い関係を築いていると感じた。
- 景観計画のなかで、マンセル値を用いるなど細かな基準を設けている。このことは、行政と市民が共感できる「まちの色」があったからであり、素晴らしいと感じた。
- 「祭りを大切する」、「川を綺麗にする」、「屋根から雪を降ろす」など、地域の活動と文化が根付いた町であると感じた。
- 市役所の方や住民がこの町をよく知り、町を誇りに思っていることを強く感じた。
- 「しまいや」という言葉を知ることができた。通常は、店じまいをすると淋しくなるが、高山の町は、新しく古いものをつくり直して、賑わいを創った町であることを知ることができた。
- 祭りなどを通じて、町の誇りを伝える伝統・文化があることが素晴らしいと感じた。
- 祭りを中心としたコミュニティがあり、その中のキーマンがまちづくりにうまく機能していると感じた。
- 景観条例が施行されている先進地として、条例の仕組みや組織がよく理解できた。
|
|
(記録:川本直義/エルイー創造研究所) |