◇総会
|
||
◇来賓あいさつ
|
||
  |
||
◇議案議決の件
第一号議案 平成17年度事業報告及び収支報告の件 |
||
◇平成17年度新規会員のご紹介の件
|
||
◇閉会
|
||
◇記念講演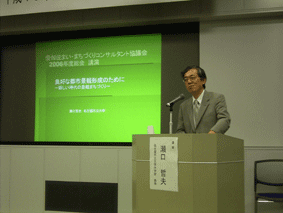 「 良好な都市景観形成のために 〜新しい時代の景観まちづくり〜
」 「 良好な都市景観形成のために 〜新しい時代の景観まちづくり〜
」瀬口 哲夫氏 名古屋市立大学芸術工学部長 |
||
◆はじめにご紹介いただきました名古屋市立大学の瀬口です。まず、多くの学協会員が減少しているといわれる中、「愛知住まい・まちづくりコンサルタント協議会」の会員が増えているというのは素晴らしいと思います。マレーシアでは、都市計画プランナーの資格制度ができ、学生が増えたと聞きました。日本でも学生が将来都市計画を目指すとき資格制度のようなものがあると良いかも知れません。いづれにしても、若い後進の人たちが夢を持ってまちづくりに入っていけることが必要で、その夢をビジュアルとして与えるのが絵やパースなどで表現力と構想力がプランナーには必要です。 ◆景観の捉え方〜蒲郡市、大府市を事例として〜景観を考えていく上で名前を付けるということは非常に大切です。名前が無いものは認識できません。蒲郡市の場合、豊富な緑地を持った都市に住んでいるという自覚をするということが必要だと考え、背後の山並みに「蒲郡山地」という名前をつけました。また、蒲郡の景観にとって海はとても重要であり海からみた陸の景観を考慮して海の上にも景観重要地区を設定しました。日本で唯一ではないかと思います。つまり、景観計画を作るときに、まずはマクロに考えることが重要です。次に、大府市の景観計画を策定したときの話ですが、大府市というところは7つのまちが合併してできており、中心がないような農村集落ですから、景観計画を作るのが非常に難しかった。そこで、7地区の山、丘をまちのシンボルにして、地区の人たちが相談して決める公園を作れば、市民が作った景観ができるのでないだろうかと考えました。景観基本計画というのは、やはり目に見えるものが中心になっています。そのようなコミュニティや町の歴史そのものを反映した景観計画を作っていくことも重要でないかと思います。 ◆都市計画の制度について1970年代から町並み保存の話が出てきて、妻籠が伝建地区に指定されるなど景観が考えられるようになりました。その後、90年代に入り都市計画マスタープランや登録文化財などの制度ができました。私は、建築確認は民間の資格のある人に委任していてよいと思いますが、集団規定のまちづくりや都市計画はコンセンサスを得る形でチェックする必要があると思います。つまり、都市景観上、建築だけではなく、都市がどうあるべきかという制度にならないといけないのでないかということです。日本の場合はそのような都市計画の制度が十分でないためにまちづくりが非常に不十分な形で進んでいると思います。◆景観と環境の質名古屋市は、環境首都を目指すとのことですが、1980年代から90年代にかけて景観基本計画には、環境の質に対する配慮が少し弱かったと思います。以前、医学部の先生が「景観の基本は平安時代の枕草子にある」と言われました。つまり、家に帰ったときに緑があり、早春にはウグイス、秋になると庭の虫が鳴いているという自然との共生が景観の基本だということです。景観を考えるときには、そういったことも考慮して下さいと言っておられましたが、当時のものは、環境の質のという視点が弱かったのでないかと思います。◆「美しい愛知づくり基本計画」策定について愛知県の「美しい愛知づくり基本計画」の策定委員会の座長を努めましたので、この中で定めた基本目標についてお話します。ひとつは、愛知県の歴史は武家文化以外にも近代都市計画でもあると言う議論から"武家文化や近代型遺産が伝える歴史景観をのばしていこう"という景観目標を定めました。また、自然と共生するというのは、我々が中山間に入って使うことだけではなく、そこに多様な生物が住んでいるということを景観で保証できないかという考え方から"多様な生物が共存する自然景観"を定めました。さらに、虫の音が聞こえるような住環境や窓の外を見れば自然があり、直ぐ近くに広い公園があるなど、コミュニティや日常が景観の基本だと考え"暮らしてよく訪れてよい心の豊かさを映し出す生活景観"なども定めました。策定にあたっては、目標案をホームページで公開し、県民の意見を受けて変更されたことも多く、県民参加の一つのあり方も示されました。しかし、委員会では、目標だけではなく具体的にアクションを起こさないといけないとの強い意見があり条例を作ることとなったわけです。これが3月の終わりに公布されました"美しい愛知づくり条例"です。 委員会での議論を紹介致しますと、ひとつはランドマークがある所は景観に対する意思の統合が図りやすいということです。たとえば、西尾市の場合、愛知県版1億創生事業として城跡の整備を行いました。それがきっかけとなり、旧近衛邸が整備され、鍮石門が復元され、住民の意識は変わりました。犬山市の場合でも国宝犬山城の城門をまちづくり交付金で板張りするなど、ランドマークがあれば住民の意識がそこに集中していきます。ランドマークがないところは新しく見いだせばよいと思います。 それから景観の質も議論になりました。名古屋の中心街活性化計画策定の際にはデザインのなかに「おしゃれ」という価値観を入れて欲しいとお願いしました。たとえば横浜で行われているものを真似てデザインがあるといってもダメだと思います。やはり質が問題であり、物真似しないということが重要です。 ◆地域への愛着が景観をつくる景観行政団体が岐阜県で7団体、静岡県で3団体、愛知県で2団体、三重県でゼロと中部地域内ではとても少ないです。是非、コンサルの皆さんには景観行政団体を増やしていただくよう努力して貰いたいと思います。一方、愛媛県や神奈川県の14団体など多いところもあります。これらは行政の姿勢が反映されている結果ではないかと考えています。三重県は、景観行政団体はゼロですが、景観条例は多くありますので景観法までいかなくてもよいと考えているのかも知れませんが、そこには何か乗り越えられない壁があるかとも思います。景観法によって強制力は非常に強くなりましたが、強くなった分、適用することにも抵抗力があるかもしれません。それを考えると景観法と条例と2段階で行う市町村がでてくるかもしれないと考えています。いづれにしろ、美しいまちづくりへの強い意思と歴史観を持つことが必要だと思います。 "美しい"という言葉だけでは皆ついてきません。地域への愛着、どうしてもここが良いという、あるいはこういうまちを後世に引き継ぎたいという強い意思を持ってもらうということが必要です。 ◆事例「連続性が途切れ魅力が半減する歴史的町並み」歴史的な街並みには必ず大きい家があります。そのような家は相続の際に手放すケースがままあります。敷地が広いため高層マンションがつくられたりします。これを防ぐため、高度地区などの手法を使ってまちづくりをするとこが重要だと思います。 「都会の中の歴史的景観の奇形」 東京の事例ですが、ビルの下に無理矢理つくった神社の参道や能舞台です。計画した人は一生懸命やったと思いますが奇形です。 「失われつつあるまちの彩り」 刈谷市の事例ですが、政策投資銀行の藻谷さんが"日本一衰退している商店街"として紹介をされています。しかし、ものづくりの世界に冠たる愛知県で刈谷は注目に値するまちです。工場だけではやはり寂しく、常滑や瀬戸のようにまちと同時に産業もあるというような感じであれば良いと思います。 次は、亀崎にある2、3m程度の路地ですが、昨年度の半田市都市景観賞を受賞しました。都市景観賞の銘板を町内会長に渡したらどうかという話がでました。一方で狭い道を無くす計画が進行しているように聞いていますが、町内の人に意識していただき、誇りを持って大切にして貰えれば良いと考えております。 「良好な自然環境を阻害している人工物」 日本橋の上に高速道路を通していることや大阪の中之島など事例は多くありますが、これは、日本三景松島の対岸にある火力発電所です。日本三景にこのようなものがつくられることは景観に対する意識が弱かったのだと思います。 次は、木曽川沿いのマンションです。42m程度のマンションですが即日完売だそうです。しかし、都市景観から言えばおかしいということで国交省、犬山市、各務原市含めて今後の対策を検討されているそうです。一方で、岐阜駅前の清水川では私ども子どもの頃にあったような多自然型の川が再現されており景観に配慮していることが伺える事例もあります。 |
 ◇開会
◇開会 都市調査室の高田弘子氏を議長に審議。原案通り可決された。
都市調査室の高田弘子氏を議長に審議。原案通り可決された。
 ◇新代表・役員あいさつ
◇新代表・役員あいさつ 知多有料道路の野立て看板
知多有料道路の野立て看板