片桐 常雄 氏/インターネット活用による政策形成−藤沢市市民電子会議室
松浦 さと子 氏/インターネットとNPO−藤前干潟保全のとりくみ
藤村 洋一 氏/商店街の活性化とインターネット−早稲田商店会
桑村 武志 氏/建築主と設計者をつなぐネットビジネス−ハウスコンペ
[コーディネーター]
小栗 宏次 氏(愛知県立大学教授)

[パネラー]
片桐 常雄 氏/インターネット活用による政策形成−藤沢市市民電子会議室
松浦 さと子 氏/インターネットとNPO−藤前干潟保全のとりくみ
藤村 洋一 氏/商店街の活性化とインターネット−早稲田商店会
桑村 武志 氏/建築主と設計者をつなぐネットビジネス−ハウスコンペ
[コーディネーター]
小栗 宏次 氏(愛知県立大学教授)

片桐 常雄 氏/インターネット活用による政策形成−藤沢市市民電子会議室
【藤沢市市民電子会議の紹介】
・運営:市民から公募した運営委員会が運営。市役所の運営ではない。
・発意:会議室は市民エリアと市役所エリアに大きく分かれている。
市民エリアはテーマを自由に設定して個々の会議室を開設。バンドル名OK。39会議室。
市役所エリアは運営委員会がテーマを設定して開設。実名発言、7会議室。
(市役所エリアはマスタープラン的なテーマが多く、具体性がないのであまり盛り上がらない。)
・議論:電子会議室でコミュニケーション、画像の使用が有効、
・合意:評判ボタン(拍手・賛成など)、投票、進行役によるまとめ
・提言:運営委員会から市、市長へ提言
・閲覧は誰でも可能、発言する際は登録が必要
・会議室を開設できるのは市内在住在勤
・参加状況:99/06〜00/09のアクセス数104千アクセス、登録者1107人、発言数8781
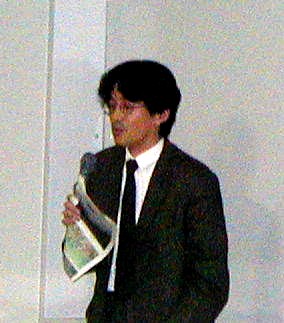 【引地川ダイオキシン問題】
【引地川ダイオキシン問題】
引地川で高濃度のダイオキシンが検出した新聞記事が00/03/25に掲載されました。すぐに市役所へ問い合わせても混乱していて答は返ってきません。早速、そのテーマで電子会議室を開設したら、驚くほどのアクセスがあり、多くの現場情報が寄せられ、活発な議論や情報交換が起こりました。引地川の橋の写真を公開し続けているホームページが突然注目を集めたり、地元サーファーが自分の体は大丈夫かという質問に環境の専門家が回答するなど、様々なレベルでの市民間の情報交換がありました。
【くげぷー跡地利用】
市所有地で小田急が営業していたプールが突然閉鎖、市に返還されることになりました。その跡地利用について市民が先行的に議論し、様々なアイデアを提言しました。その結果、市民参加の形で市が跡地利用を検討することになりました。その途中で、ある市民が市議会の議事録を個人のホームページでアップしはじめ、結局は議員会館が自ら議事録をインターネットで公開するようになったりしました。
【まちづくりへの可能性】
電子会議室は情報カフェとでも呼ぶような、昔のパリのカフェのように市民の情報交換や世論形成の場としての役割を担っています。目的指向ではなく、たまり場での与太話のなかから市民の発意が現れてくる。また、専門性を持った市民の参加や、実際の集会では不可能なほど大人数の参加が可能になります。写真を使った現場情報など市民からの情報提供がダイナミックに得られることも利点です。その他、情報データベースとしての会議室など、様々な可能性が広がりつつあります。
松浦 さと子 氏/インターネットとNPO−藤前干潟保全のとりくみ
藤前干潟をゴミで埋める問題が起こったとき、名古屋市民の多くは藤前干潟の存在を知りませんでした。埋め立て計画が起こった当時の港区の小中学校の生徒の「将来の港区」(1985年)という作文集が残っていますが、そこには鳥や干潟のことはなく、鉄腕アトムの手塚治虫的な近未来像が描かれていました。
(日本湿地ネットワーク制作のビデオを上映)
これはコスタリカで藤前干潟保全の報告がなされた際に、世界中の人々に披露された映像です。藤前干潟を守る会の辻さんは今、日本湿地ネットワーク代表として、この干潟を都市と共生するモデルとして紹介され、諫早湾にも干潟を取り戻そうと働きかけておられます。
 保全活動の中心的存在の辻さんは、保全が決まる2年前までは紙の媒体で保全を訴えておられました、その後はホームページやEメールも積極的に使って、地元の市民や市民団体への呼びかけと、全国の環境保護に関心をもつ人々への呼びかけをされ、多様な領域のそれぞれから違った形での協力を得られることにもつながりました。
保全活動の中心的存在の辻さんは、保全が決まる2年前までは紙の媒体で保全を訴えておられました、その後はホームページやEメールも積極的に使って、地元の市民や市民団体への呼びかけと、全国の環境保護に関心をもつ人々への呼びかけをされ、多様な領域のそれぞれから違った形での協力を得られることにもつながりました。
辻さんの活動は長期間に渡って蓄積された干潟や生物達の詳細なデータに基づいておられたと同時に、辻さんのメールが非常にジャーナリスティックな視点や文学的な表現力をお持ちであったこと、そして相手を思いやりながらメールを発信されたことが共感を呼びました。例えば、大荒れに荒れた公聴会の議事録をそのままメーリングリストで全国に発信するなど。そうした辻さんの呼びかけに、市民だけでなく様々な分野の専門家が反応し情報提供を寄せました。埋め立てに関する工学系の専門家だけでなく、鳥類や海洋生物の専門家、都市計画、行政学、法学、経済学、などの分野からも。
インターネットをお使いになられたことでこれまでと大きく違ったのは、地方から中央を経由せずに全国に情報発信できるようになったことと、海外へ直接情報発信できるようになったことです。海外からの応援メールは名古屋市内からよりも多いくらいでした。オーストラリアの鳥類学会の前会長をはじめ世界中の干潟の専門家から環境庁や愛知県、名古屋市に対して直接メッセージを発してくれました「日本の片隅を守れない人に世界の環境問題が問えるのか」と。世論、環境庁等いろいろなプレッシャーがあったんでしょうが最終的には名古屋市の大英断によって藤前干潟を守ることができました。
最後に、インターネットによって辻さんは次の3つのことを可能にされたと思います。「情報を開くこと」「情報をつなぐこと」「情報を分け合うこと」。公開されたコミュニケーション>によって合意形成がなされること。様々なところで研究されていた情報がインターネットで一つの方向につながっていくこと。情報格差があるなかで格差を無くすように情報を多くのひとで分け合うこと。これらによって藤前干潟の保全が可能になったのだと思います。
藤村 洋一 氏/商店街の活性化とインターネット−早稲田商店会
最近、早稲田商店街はエコや活性化で有名になり、ちょくちょくテレビで紹介されたり、全国から見学者が絶えないほどの有名ぶりです。実は最近、地元の小学校で2クラス81人の児童が突然増えたんです。不動産屋が"有名な環境の街早稲田に住みませんか"とうたってマンションを売り出してるじゃないですか。商店街の見た目は特に変わらないんだけど、住んでる我々の方がビックリしました。
さて、そんな早稲田商店街ではどんなことをやっているかご紹介します。早稲田商店会はご存じのように早稲田大学を囲むようにあります。ここには約3万人の学生がいて、周りの住民は約2万人いますが、夏休みにはその3万人の学生がいなくなっちゃう。そこで4年ほど前から夏枯れ対策として夕涼みコンサートをやることになった。ところが資金がないので大したミュージシャンは呼べず、人も集まらない。そこで、最近の環境ブームに当て込んで「エコサマーフェスティバル 環境と共生 今早稲田から」と銘打ってゴミのでないイベントをやることにしました。空き缶やペットボトルの回収機、生ゴミ処理機などのメーカーに呼びかけて、出品してもらった。そうした試みがNHKをはじめ読売新聞、朝日新聞などのマスコミで大々的に取り上げられ、有名になりました。そこで調子に乗って、今度は学生のいる11月にも開催して、これもまた大成功を納めた。ここから空き店舗を使ったエコ事業が恒常的に行われるようになったんです。
(商店会が紹介された朝のニュースの録画ビデオを上映)
 紹介したラッキーチケット空き缶回収機は「お客も店も楽しくて儲かるリサイクル」と言われてます。普通は、地下鉄出口などで配っている割引券ではなかなか客は集まらないけれど、不思議なことに空き缶回収機で当てた割引券だと、同じ割引券でもほとんどのお客さんが店にやって来る。情報の出し方によって効果は大きく違うんです。こうした取り組みによって、商店会は地域を大切にしなければダメだということを改めて気づかされました。客を消費者とよぶ量販店とは違うんだということを。
紹介したラッキーチケット空き缶回収機は「お客も店も楽しくて儲かるリサイクル」と言われてます。普通は、地下鉄出口などで配っている割引券ではなかなか客は集まらないけれど、不思議なことに空き缶回収機で当てた割引券だと、同じ割引券でもほとんどのお客さんが店にやって来る。情報の出し方によって効果は大きく違うんです。こうした取り組みによって、商店会は地域を大切にしなければダメだということを改めて気づかされました。客を消費者とよぶ量販店とは違うんだということを。
そこで、商店会長が折角だからそれぞれのお店で量販店にはない「こだわりの商品」を出そうということになりました。ところが、こだわり商品を探しても自分の店には量販店と同じものしかないことに気が付いたんです。この問題は根が深く、量販店は日本の流通を変えてしまったので、今では大手量販店向きの商品しか流通しなくなっていたんです。じゃあ、地域の人達に我々商店会は何を提供するのか、という原点に帰ってまた考えました。
そこで全国の地域や商店街をよくみてみると、量産できなかったり、ちょっと形が変わっていたりするために量販店の流通から落ちこぼれている商品が意外とたくさん残っていることがわかった。例えば、農業高校の実習でつくった米、ハム、ケチャップがある。これら全国の農業高校をネットワークして売り出そうと今準備しています。
実はこの8月にそういった40くらいの商店街を集めて会社を作りました。そこに現役の高校生社長をあてました。そしたら、修学旅行で見学に来る中学生らのメーリングリストを作っちゃった。ダイレクトメールもインターネットなら簡単ですし、中学生は将来のお客さんです。
早稲田商店街でも新しい商品を開発しました。"大豆畑トラストMy豆腐作戦"と呼んでますが、4000円で10坪の大豆畑の臨時オーナーになってもらう。収穫した国産有機栽培大豆は商店街の豆腐屋に直接送ってもらって豆腐に加工して小作料としてオーナに渡す仕組みにしました。毎週木曜日にMy豆腐ができるので取りに来てもらう。これが地域の人にすごい好評でした。ところが、うっかり取りに来るのを忘れてしまう、それで電話でお知らせサービスや配達もすることになった。それによって、地域と商店会の結びつきもまた深まっていく。そうすると今度はうちの小麦を使ってくれといってくる、そして"小麦トラストMyパン作戦"になり、そうしていろいろなメニューが増えてくると同時に、全国の商店会のネットワークができてきた。これは比較的若手同士のネットワークになっています。得てして、それぞれの商店会で頑張って孤立しちゃったような人がネットワークに夢中になるので孤独な同志で強いネットワークが全国にできた。コンピュータの使い方は街の障害者の方に教わりました。
こうしたネットワークはリサイクルを発端にできあがってきたんです。先ずは地域があって、そして人のつながりがある。我々はそれにITを利用していると言うことです。
桑村 武志 氏/建築主と設計者をつなぐネットビジネス−ハウスコンペ
【ハウスコンペの概要】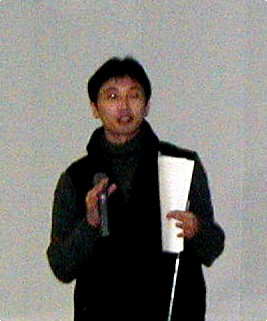
ハウスコンペは1997年2月に開設した住宅設計コンペのホームページです。施主と設計者がダイレクトに出会える場として立ち上げました。コンペ自体に新しさはないのですが、インターネットで行うことで、そこそこ面白いものになってきていると思います。活動は、ほぼオンラインのみ、運営は個人で行っています。ボランティアではないけれどもネットビジネスといえるようなものでもありません。現在(2000.11.10)までに、36件のコンペが行われ(進行中を含む)、7〜8割の確率で設計契約まで至り、既に11の物件で竣工を迎えています。登録設計者は900名近くになっています。最近は関東以外にも関西でも協力者を得て展開している。残念ながら今のところ名古屋での申込みはない。
(会場でホームページの内容を上映して説明)
私は一度は設計事務所に就職したのですが、住宅設計の依頼は雑誌の作品を見てかコネによるものがほとんどで、このまま10年勤めて独立しても自分が依頼を受けることは難しいと思ったんです。そんなときインターネットが急速に広まって、これをうまく使えないかというのでインターネットによるコンペを思い付いたんです。もともと家で仕事をしたいと思っていたし、人嫌いな面もあって、インターネットの距離感がちょうど心地よく、自分に合ったワークスタイルを見つけたと思っています。
建築設計者は自分のホームページを持っている人が結構多くて、最近は一般の人の目に触れる機会も増えたんではないかと思います。その点で設計者の敷居の高さというものは随分下がってきたと思いますが、まだまだ一般の人が建築家に設計を頼むことは難しい面を持っています。例えば、最近は建築条件付きの土地が多く、土地だけの物件を個人が見つける難しさ、すぐに着工したい施主と設計者のスケジュールとの不都合など。
ハウスコンペを始めてからは、個別の住宅設計だけでなく少し面的な住宅開発の相談も受けたりしていて、そういう仕事にも興味が移ってきています。名古屋でも仕事があれば是非お声かけください。
意見交換
 (小栗)
(小栗)
残念ながらもう時間がなくなってしまいましたので、これからのITを使ったまちづくり、ITを使った住まいづくりについて、他のパネラーの活動紹介への意見なども含めて、それぞれお一人づつコメントしていただいて終わりにしたいと思います。
(片桐)
他のパネラーの話を聞いて思ったたんですが、藤沢も発言者の約6割が市内から、3割は市外からなんですが、その市外の方は建築家や弁護士や環境NPOの方などで、残りの1割は行政や議員の方という構成になっています。一つの問題に対して、その地域に密着した地域のネットワークと、そのテーマに関連する専門家や同じテーマを持つ団体などとの全国的なネットワークとが重層的にできあがる。それを地域の縦糸とテーマの横糸と考えるとその交点にあるのが、先ほど小栗さんの言われた地域ポータルサイトになるのではないかと思います。藤沢の場合はそれを行政がやっているが、本当はNPOが担った方がいいと思います。しかし、一般に比べてNPO活動の参加者の方がデジタルデバイドを利用している割合が低い現実もあり、ITをまちづくりへの活用する際にもその辺が課題になるでしょう。
(松浦)
現場で忙しい人ほどコンピューター前に座れる時間がどうしても少なくなってしまう現実は確かにあります。インターネットは現場を補完するポジションでなければならないし、リアルとバーチャルが分離してしまう懸念は常に注意すべきです。また、インターネットが不得手な人が情報で孤立しないよう、それ以外の様々なメディアを使って情報を分け合うことも重要です。
藤前干潟を守る会がやっていた地元向けのメーリングリストでは、守る会以外のメンバーが教わることばかりで守る会が得る情報は少なかったと思います。しかし、守る会が干潟写真展の会場候補をメールで尋ねた時に、守る会以外のメンバーから各地域の情報がドッと集まり、守る会はとても力強く感じたそうです。
藤沢電子市民会議も拍手ボタンがあったりして、意見に対する共感の気持ちや応援の気持ちを集める工夫がされています。こうした細かな工夫をこらして、様々な地域のネットワークが生まれることをこれからのITに期待します。
 (藤村)
(藤村)
商店会に参加して一番感じることは、地域や町場ということを意識する事が大切と思う。住まい・まちづくりを職業とする人達は"生活感"を持つべきです。早稲田はとても身近なところから発想しました。環境とは何か、身近な環境は近所付き合いではないか、近所付き合いをお役所やコンサルタントにまかせてどうすのか、という自問から取り組んでいったんです。
そういう近所付き合いの会合でもメールを使うことは充分メリットがあります。一家団欒の夜の時間に全員が一箇所に集まらなくてもいい。昼間でも夜中でもちょっと空いた時間にメールを呼んで発言すれば会合ができる。みんな酔っぱらってなくて真面目な話ができます。
それと、へんに足並みを意識しないで「やりたい人がどんどんやる」というのでいいのではないかと思います。早稲田商店会でもやる気のある若い者にまかせていると、若い者どうしのメールのやり取りで次々面白いことをやり始める。それまで関心のなかった商店会長なんかの年長者も置いて行かれるんじゃないかと不安になって、慌ててメールに参加し始める。それでいいんです。
(桑村)
ITで何を実現したいのか、それは本当の豊かさだと思います。物の時代は終わって、私はベンツ持つよりも"時間"がほしいですし、情報社会だからといって情報をいっぱい持っていることが豊かだとも思いません。ITが直接住まいを変えるんではなくて、ITでライフスタイルが変わって、その結果で住まいが変わるんだろう。自分はネットビジネスをやっている意識はなくて、年収だって100万ちょっとしかないが、共稼ぎの妻と一緒にそれで食べていけるし、充分豊かな生活を送っている。私からみると一般のサラリーマンは稼ぎすぎで、それにこだわることでかえって窮屈な生活になっているんじゃないかと思います。
(小栗)
もっとお話を聞きたいところですが、時間がオーバーしていますので、この続きはフロアーでそれぞれの皆さんと意見交換したいと思います。本日はありがとうございました。
(文責:藤森((株)日建設計)