◇ 基調講演 「ITとライフスタイル・ワークスタイルの変容」小栗宏次 氏(愛知県立大学情報システム学科教授)
|
||||||||||||||||
【ITはインフラであり環境である】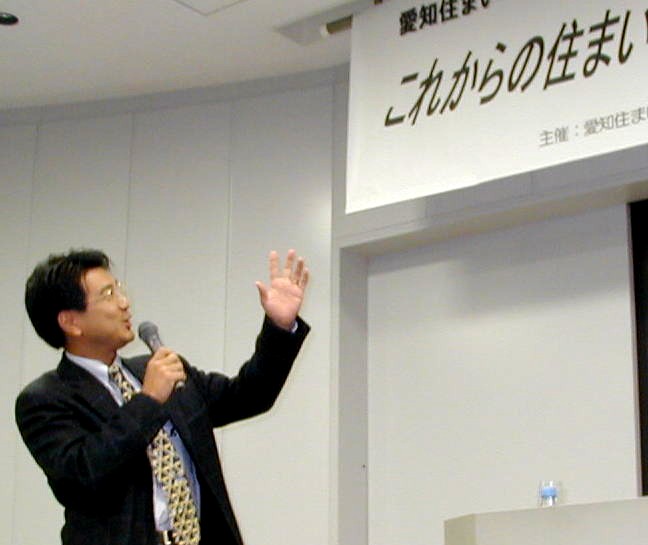 最初に本日のシンポジウムのタイトル「これからの住まい・まちづくりはIT(情報技術)で変わるか」をお聞きしたときに、実際は逆じゃないかと思ったんです。つまり「ITが住まい・まちづくりでどう変わるか」といった方が適当ではないかと。ITは道具ではなくインフラであり環境なのです。これからのまちづくり活動がITという環境を変えていくんです。 以前、アップルコンピューターのマッキントッシュ(Mac)が日本に入ってきたころ、医療カルテなどにとても便利なのでお医者さん達に使い方を教えて回しました。ところが、1、2年もすると立場が逆転して、こんな使い方もあるよ、なんてお医者さん達から私たちが教わったりするようになってしまいました。よく考えれば当たり前です。お医者さんの方がコンテンツが豊富なんですから。医療分野がITという環境をうまく活かして変えていったんです。 まちづくり分野も同様です。あと2、3年も経てばITという環境がすっかりまちづくり分野に広がっていると思います。その時はコンサルタントの皆さんがすっかりITを使いこなしている事でしょう。 (1) IT社会って何? 【堺屋太一 流のIT社会】 日本でIT社会を的確に語っている人は少なく、その一人として堺屋太一さんは経済白書の挨拶文で、IT社会は「人と人との出会い」を促進する社会だと言ってます。まさに、IT社会はインターネットやデジタル放送によって地域の人々が圧倒的に多くの人々と出会うことができる社会なのです。例えば電子政府活動など地域で活躍している人達にその活力源を尋ねると、自分の組織の上司や首長の理解よりも、ネット上で知り合った多くの仲間達の支援に支えられて続けているんだと答えます。まさにネット上の人と人の出会いが地域の活力を生み出しているんです。 さらに堺屋さんは、人と人の出会いが促進されると、ネットオークションなどの商品や金融の需給といった「人と物との出会い」、ネット上で即時に論文を発表するなど「技術や知識の出会い」、NPOなどの共通の趣味や関心事についての「個人的な出会い」と組織展開、などが活発になると言っています。続けて、これからの社会で重要なのはハードウエアでなくソフトウエアでもなく「ヒューマンウエア」つまり人と人をつなぐ環境であり、それがITなのです。 【高城剛 流のIT社会】 一方、別の視点でクリエーターの高城剛さんが言うIT社会は、「重要なのはインターネットによって車が買える事ではなくて、仕事が効率化されること」であり、その結果「週休3日になること」、「そのための環境・インフラがIT社会である」と言っています。さらに面白いのは、「曖昧な多層的時間の発生」つまり仕事でもあり遊びでもある時間の有効活用がとても重要と言っていることです。例えば、私が授業中に課題を出すと学生は携帯電話のiモードを使って隣のクラスの学生やゼミの先輩に即座にメールで尋ねて答を整理してしまう。授業中にけしからんのだけれど彼らは効率的に課題をこなして有効に時間を使っている。また別の人は、仕事中だろうが休み中だろうが思い付いたことは即座に自分宛にメールする。または、メーリングリストで仲間に同報通信する。家に帰ってくるころには自分のアイデアに対するみんなの意見やアイデアが返信メールで集まっている。それを編集して一つの仕事や商品になったりする。そういう人が今は大勢いる。遊びか仕事かわからない、そういう多層的時間の有効活用なのでしょう。 (2) 時代の流れとライフスタイルの変容 【今、あらためて第三の波】 人類は、採集社会→農業社会→工業社会と進んできて、今まさに情報社会になってきました。工業社会では効率性が重視されてきました。コンビニエンスストアが典型です。「工業社会のまちづくり」においても効率性が最優先されてきました。しかし、情報社会となった今は「情報の共有」に重きが置かれるようになり、そこでのインフラ・環境としてITが重要視されています。しかし、ITは決してツールではない。まちづくりにインターネットや携帯電話をどう使おうかと考えているうちはすぐに限界がやってきます。そうではなくて、インターネットの向こうにいる人々や情報をどうまちづくりに役立てるかと考えるべきです。 そして、工業社会→情報社会の次には「創造社会」がやって来ると私は考えます。創造社会では感性のある情報が重視され、創造性を伸ばして個人のニーズや個人の能力を活かしていく社会になると思います。 【キーワードの変化にみるライフスタイルの変容】
 (3) 時代の流れとワークスタイルの変容 (3) 時代の流れとワークスタイルの変容【活動の中心地の変化】 人類の活動の中心地は自然の中から、産業革命・鉄道整備を経て"駅前"が活動の中心地となりました。それが車社会となって駅前からロードサイドに中心が移り、街並みは破壊されてしまいました。そして次のIT社会においては活動中心地は"家庭"へ回帰します。家庭がオンラインで直接外とつながるようになるからです。 【スタンドアローンからネットワークへ あるいは 脳的発想から免疫的発想へ】 これまでの組織や自治は有能なリーダーがいて、その人の指示にもとづいて皆が動く仕組みでした。何か不満があればリーダーに向かって文句を言えばよかったんです。これはまさに脳から指令がでて手足が動くような「脳的発想」です。 それに対し、IT社会が進むとインターネットでみんなが直接意見を言えるようになる。問題が起これば即座に個々の意見が共感し、すぐに行動につながる。まるで、体に入ってきたウイルスに白血球が個々に対抗して体の健康を維持する免疫作用のようなことが、脳の指令がなくとも進んでいく。これが「免疫的発想」です。 まちづくりで言うと、例えば地域でゴミ問題が起きたときに、役所の遅い対応を待たずしても、市民の意見がネット上で直接共鳴して一つの民意が形成され、そしてすぐに行動が起きる。IT社会ではそういうまちづくりが現実のものとなるでしょう。 (4) ITによるまちづくりのススメ 情報インフラは電気水道のようなインフラと同様に社会に不可欠なものになります。ドイツは自転車道や遊歩道が整備されて豊かな余暇生活が実現しているし、バリアフリー環境が整備されているから車椅子でも街で活動できる。同様に情報インフラがあってはじめてIT社会のメリットが享受できるのです。 電気・水道、道路・鉄道といった工業社会のインフラが地域の発展を左右したように、この情報社会では情報インフラがなければ地域の発展や豊かな生活は実現しないと考えてください。現在の日本では道路や電気水道に比べて情報インフラは大変立ち後れているのが現状です。 公共施設は当然情報インフラが必要だし、電子庁舎やGIS(地理情報システム)などがIT社会のまちづくりには不可欠となるでしょう。まちづくりコンサルタントの皆さんには地理情報システムの大切さを理解してもらうためにカーナビのご利用を是非お勧めます。 また、IT社会になって地域がネットワーク化すると同時に地域の個人や商店の情報が外に漏れる可能性が出てきます。地域の情報公開や個人情報保護などを担当する行政部門が必要でしょうし、住民のネットワークリテラシーの確立が大切となります。  (5) 今求められる地域ポータルサイト インターネットの世界ではYAHOOやImfoseekなどのポータルサイトが必要不可欠なものとなってほとんどの人が利用しています。IT社会ではそれぞれの地域においても「地域ポータルサイト」が確実に必要とされます。ドイツでは各都市に地域ポータルサイトがあって「www.都市名.de」というURLにその都市の全ての情報がつながっています。観光案内はもちろん宿泊施設の予約から市内の映画館プログラムまで、全ての情報の窓口となっている。しかし、日本にはそこまでのサイトはありません。テレビでは地震が起こったときにNHKをつけてみる人が多いですが、そういった情報が必要なときに信頼性のある地域ポータルサイトが必要となるでしょう。 【リアルの世界で変わらないまちづくり】 ドイツでは古い街並みを残すため、建物は建て替えても以前のファサードを復元します。見た目はなにも変わらないけれど中に入っている店舗は全てホームページを持ち、オンラインでつながっています。IT社会では建物などリアルの世界は変えなくてもバーチャルの世界で大きく進歩することができます。 【21世紀への課題、個の時代・個のまちづくり】 国際化、情報化、高齢化といったこれまで高尚なテーマだったことが、IT社会では商店会のような小さなグループで取り組むことが可能になります。そして、地域にいる個々人や小グループが日本中や世界中とネットワークして大きな組織力となる可能性を秘めているんです。そうした"個の時代"がIT社会であり、その時求められるのは"個のまちづくり"でしょう。 (文責:藤森/㈱日建設計) |
||||||||||||||||