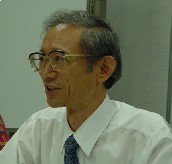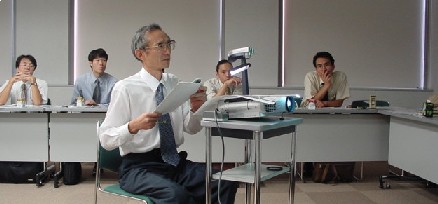日本では1992年の市町村都市マスタープランにつづき、今年の都市計画法改正によって都市計画区域のマスタープランが制度化された。これから日本では地方自治体間の広域的な計画調整が必要になると思うが、そのモデルとしてオレゴン州ポートランド都市圏の広域政府メトロを紹介する。
日本では1992年の市町村都市マスタープランにつづき、今年の都市計画法改正によって都市計画区域のマスタープランが制度化された。これから日本では地方自治体間の広域的な計画調整が必要になると思うが、そのモデルとしてオレゴン州ポートランド都市圏の広域政府メトロを紹介する。メトロはポートランド市を中心とした3カウンティと24市を行政区域とする広域政府である。市やカウンティだけで解決困難な広域課題に対応して、都市圏の成長管理・広域交通・広域公園緑地・上下水道などの都市圏レベルの計画機能と、廃棄物処理・文化施設・コンベンションセンターなどの広域施設の運営機能をもっている。
1950〜60年代の郊外スプロールやリゾート開発の問題に対応してオレゴン州は地方政府間の広域的な土地利用調整を行う制度を1973年に創設した。そこには、我が国の市街化区域のような都市成長境界線の線引きなどが盛り込まれていた。一方で、スプロールによって郊外でのミニ市の設立や、公共サービス機関である小規模な特別地区が急増し、それらの貧弱で非効率な公共サービスが問題となり、広域的に公共サービスを行う機関として1970年にメトロの前身であるメトロポリタン・サービス地区が創設された。その後、こうした広域的な公共サービス機能と広域的な計画調整機能を併せもつ広域政府をつくる提案が州議会を通過し、1979年に現在のメトロがスタートした。

現在、メトロは「リージョン2040」というプログラムを1992年からスタートさせている。2040年までの人口配置など都市圏の将来ビジョンと、これを具体化する幹線道路および公共交通計画、都市成長境界線の管理など部門別の広域フレームワーク計画が示されている。「リージョン2040」には拘束力はないが、地方政府の計画を審査する権限をもつことで、各地方政府計画へ反映することができる。
「リージョン2040」では一昔前の「成長の抑制」の考え方から、適切な成長を受け入れながら管理する「賢い成長(スマート・グロウス)」という成長コンセプトが採用されており、これからの日本の都市計画の参考となるだろう。