

【日時】 2000年7月11日 10:00~12:00 【場所】(財)名古屋都市センター第3会議室
(社)地域問題研究所 松村久美秋氏


広域行政に注目する理由は、①生活圏の広域化、②住民要求の多様化・高度化、③効率性の高い行政運営、④活力ある地域づくり、⑤地方分権への対応の5つである。
広域行政の2つの道として、「広域連合」と「合併」がある。しかし、介護保険などで増加している広域連合は、実質的には地方分権の受け皿になりえておらず、有効なのは「合併」であると思われる。
合併のメリットとしては、直接的効果と間接的効果がある。直接的効果とは、合併が行われた場合、「住民負担は最低レベル、サービスは最高レベルの自治体に揃えられるのが一般的なので、住民にとっては得」だと言うこと。間接的効果としては、経費節減/財政力の向上/適地適合の土地利用の実施/質の高い施設整備/行政サービスの高度化により地方分権の受け皿としての機能を持つ/都市のイメージアップなどがある。特に、直接的効果をもっとアピールすることで、住民の合併への合意が得やすくなる。デメリットも色々言われているが、合併することのメリットの方がずっと大きいのではないか。
住宅金融公庫名古屋支店広報課 嘉藤 鋭氏
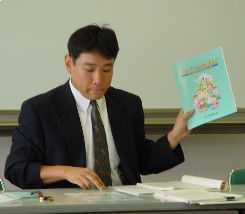

これまでの公庫の制度は、全国一律に適用されるものであったが、この制度で初めて地域性を考慮した。住宅マスタープランで、具体的な基準が定められていることが必要。金利が高めの融資のため、実績はまだ少ない。
地域要件、事業要件、建築物要件を満たす場合、最も低い金利で、公庫制度の中では最長期間(最長35年)の融資を受けることができる有利な制度。
① 2以上の敷地を1の敷地とすること。
② 新たに建設される建築物の敷地面積が100㎡以上であること。
③ 新たに建設される住宅の戸数又はその延べ床面積の合計が、建替えにより除却される住宅の戸数又はその延べ床面積の合計以上であること。
工業地域、工業専用地域、商業地域(容積率600%以上)を除く用途地域内にあり、かつ、特定の法律などに定められている地域であることが要件である。ただし、名古屋市全域が含まれる一方で、主要な地方都市の中心部が含まれていないなど、地域設定には問題もある。これをカバーする方法として、中心市街地活性化法や住宅マスタープランなどで位置づけられた地域にも適用されることになっている。
条例により定められている地域について、新築・リフォームに対し割増融資を行う。
(文責:伊藤彩子/(株)都市研究所スペーシア)