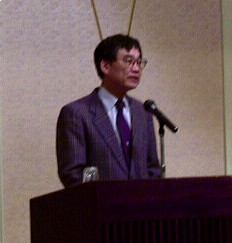
山岡義典 氏(日本NPOセンター 常務理事兼事務局長)
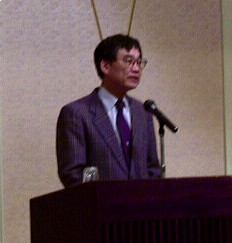
現在は、縁と恩で包まれて仲間で支えあう「世間型社会」から、個人が自立し、自己責任を基本とした人間関係で成り立つ「市民型社会」への大きな転換期である。15年ほど前のプラザ合意により「市民型社会」への移行が始まり、阪神・淡路大震災を契機とし、NPO法施行(1998年12月)、公的介護保険の開始(2000年4月)、省庁再編、情報公開法施行(2001年1月)など、21世紀に向けた制度改革が行われている。
介護保険や地方分権をはじめとする一連の制度改革は明治維新や戦後改革に比べ内発性が強く、黒船的要素は弱い。あらゆる制度改革はNPOが社会の中で育たって初めて機能するが、NPOが育つ前に既に始まってしまったため現在では中途半端である。今後のNPOの成長を待って市民型社会に移行して行く。
NPOは簡単に言えば個人の志を社会的な力にする仕組み、であり市場で供給できないサービスを社会的な支援によって民間で供給する仕組みである。
NPO(非営利組織)とFPO(営利組織)とは連続的であり、運動性、ミッション(社会的な使命)指向なのがNPO、事業性、営利指向なのがFPOである。ミッション志向と営利志向のあい重なる部分に位置するのが「こだわり事業」、つまりコミュニティ、環境、芸術といった特定の分野にこだわって取り組むことであり、これが今後の市民型社会における役割として重要である。企業も営利追求だけでなく社会貢献などミッション志向も取り入れたり、一方、NPOも活動を継続するためにはミッション志向だけでなく事業性も追求するようになってきており、双方とも「こだわり事業」に近づきつつある。
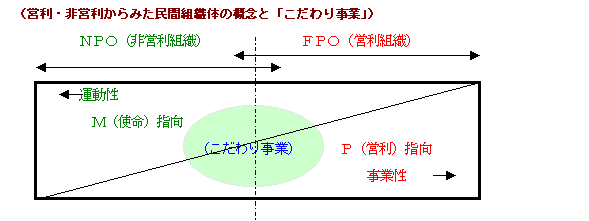
コンサルタントにおける営利と非営利の問題は、受託事業中心か自主事業が中心かで考えるとわかりやすい。受託事業は営利部分であり委託者の意向に添うこととなるが、自主事業は第三者的立場に立ちNPO的な役割を果たすことができる。日本ではNPOとFPOとが明確に分かれるのではなく、一つの組織の中で両方の機能をもつ場合が多いが、営利と非営利の配分などそこで両立することの難しさがある。
もともと弁護士や医者などの専門職は「プロボノ精神(pro-bono-pubulico(ラテン語)=For
Good Public)」つまり公共的な仕事に携わる者としての責任を負うという意識がある。住まい・まちづくりのコンサルタントにもこの「プロボノ精神」が大事である。建築関係でも住宅改造など、専門職によるNPO設立の動きも各地で出てきている。
この協議会のように専門職が協同してNPO的な活動を行うことには次の3つの点で意義がある。
第一に同業者組織は、世間型社会においては仲間内の利益を守るための組織であったが、市民型社会においては専門的な技量を活かして社会に貢献する組織というように変わりつつある。この市民型社会における同業者組織のモデルはまだできておらず、今後どのようにつくっていくかは愛知・まちコンの課題となろう。
第二に専門職には研ぎ澄まされた人権感覚が求められる。たとえスペースは小さくてもバリアフリーに配慮するほどの意識は必要で、そこでコンサルタントが果たす役割は大きい。
最後にこれまでまちづくりにおいて地域との絆を深めてきたコンサルタントが、協同してNPO的な活動を行うことにより、さらに地域のより強い信頼を得ることができる。
(文責:浅野健/㈱都市研究所スペーシア)