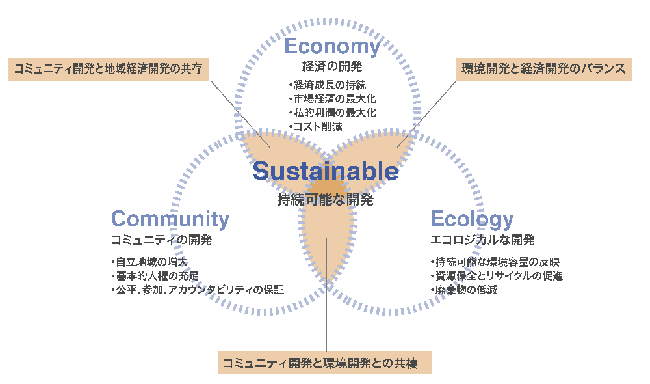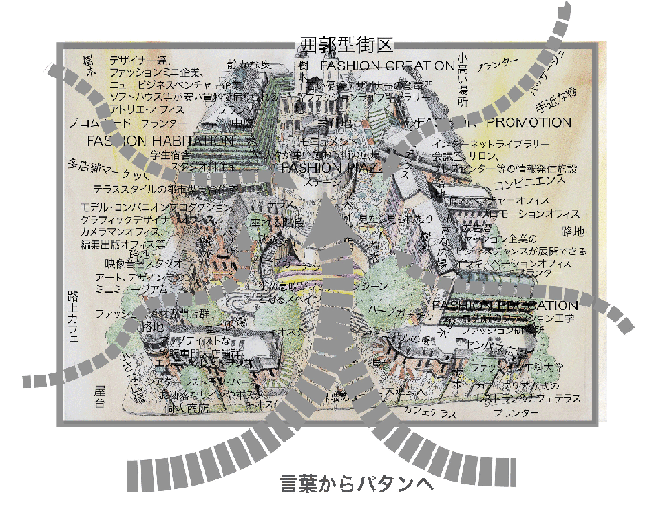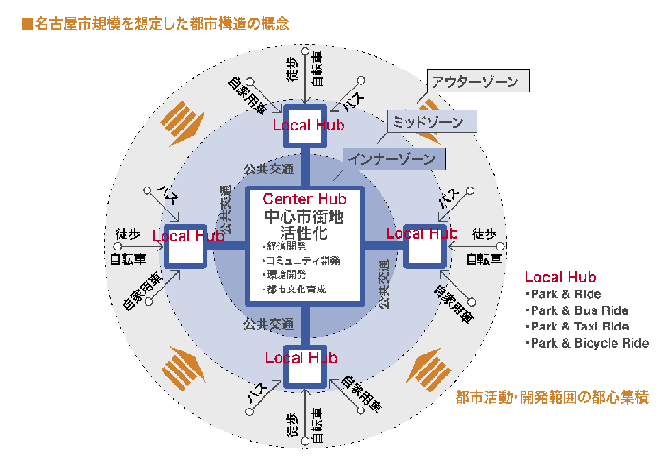|
愛知住まい・まちづくりコンサルタント協議会・2006年度公開シンポジウム
よみがえったか?中心市街地
基盤整備と商業・住宅をあわせて整備した中心市街地の報告と
建築・都市開発の提案段階におけるプレゼンテーションの手法の学習
【日時】 2006年12月20日(水)13:30〜16:30
【場所】(財)名古屋都市センター 11階大研修室
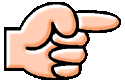 案内ちらしはここ 案内ちらしはここ
|

|
■次 第
■事例報告
(1)ダイナミックな事業展開―春日井市勝川地区の取り組み
講師 春日井市 勝川地区総合整備室管理指導課 主幹 林惠司氏
(2)大正ロマン溢れるまち―彦根市四番町スクェアの取り組み
講師 彦根市本町土地区画整理組合・彦根市本町地区共同整備事業組合 理事長 西村武臣氏
■講 演
「都市再生を図るイマジニアリング〜開発のデザイン手法について」
講師 三上訓顯氏(名古屋市立大学大学院 芸術工学研究科 教授) |
■事例報告
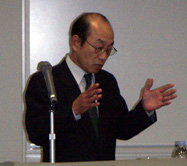 (1)ダイナミックな事業展開 ―春日井市勝川地区の取り組みー (1)ダイナミックな事業展開 ―春日井市勝川地区の取り組みー
春日井市 勝川地区総合整備室管理指導課
主幹 林惠司氏
|
- ルネッサンスシティ勝川と題して春日井市の勝川地区におけるまちづくりの取り組みについて紹介する。
- 春日井市は、面積は93k㎡で細長い市域である。一番名古屋に近いので名古屋とのつながりが強い。昭和18年と昭和33年に町村合併をして現在の市域になっている。人口は昨年の6月に30万人を超した。
- 春日井市は区画整理を主要な整備手法としてまちづくりを行ってきた。市域の約半分が市街化区域で、市街化区域の75%を区画整理事業で整備してきている。
- 勝川地区は春日井市の西の玄関口としての整備を図っていこうということで、まちづくりを行ってきた。
- 春日井市は区画整理が盛んで、現在もやっているが、昭和60前後から、区画整理の手法の中にまちづくりということを取り入れたらどうかという話が多くなってきた。区画整理で整備しても上物整備については、地権者任せであった。それではまちづくりにならないのではないか、ということで、勝川地区の整備を行うにあたって、面整備は区画整理で行い、上物整備は各種の事業手法を取り入れましょうということで、昭和61年に「勝川駅周辺総合整備計画」を策定した。
- 総合整備計画では、面整備である区画整理事業と市街地再開発事業・地下駐車場事業・住宅市街地総合整備事業(密集市街地整備促進事業)・鉄道高架事業を計画した。
- 地元へのアプローチは、商業集積がそこそこあることから、商業の活性化を含めて計画を作ったことから、商店街の人を集めて、1年間、毎月、毎月、計画の内容及び商業の近代化について勉強会を実施した。
- 勝川駅前の区画整理は昭和62年から実施している。ここでは、商業集積の現状・商業の近代化等のまちづくりの視点から、区画整理事業と再開発事業の一体的な施行を行ってきた。勝川駅前の区画整理は減価地区であり、土地の先買いを行ったが、地区が良くなるのに何故売らなければならないのか、ということから、売り手が少なかったため、減価補償金を使って立体換地手法を導入し、対応した。それにより減歩が軽くなるとともに、再開発事業をスムーズに進めるために、行政が先行して上物整備を行うことで、弾みがつくと考えた。しかし、再開発事業については、再開発で何を整備するのかの検討が長く掛かり、ようやく来年完成である。
- 総合整備計画を実施していくため、地権者の考えを確認するため、各戸個別にアンケートを実施した。それにより、勝川のまちづくりへの理解が得られるようになったと思う。
- 再開発は6つの街区でおこなった。それぞれは、小さな街区であるので、6つの街区で一人前と考えた。そして、それぞれの街区で役割分担を設定し、用途を検討した。その計画策定にあたっても、各街区の代表者を集めて勉強会を行い、推進計画を策定した。
- 事業計画の策定にあたっては、国から3分の1は補助が出るが、残りの3分の1を地元の人の負担とし、借金をしてもらった。その借金をしてもらったことによって、十数年再開発組合がつぶれることなく日の目を見ることができた。その時の事を振り返ると、行政が100%お金を出していたら、いつつぶれても良いということになり、計画を作っても前に進まなかったかもしれない。
- 再開発事業により400戸の住宅が出来るが、人口が増えることによって、子供の数が増えて、学校の収容人数の拡大が必要であるのでは、と心配したが、松新地区の188戸の購入者は、高齢者やこれから子供をつくる若い夫婦が多く、2極化した購入者であった。
- 鉄道の南は、駅の南は長屋等の密集市街地で防災上危険な地域であったが、基盤整備を区画整理事業で、上物整備を密集事業で一体的におこなった。区域内外にコミュニティ住宅を建設し、地区内から移転してもらい、密集市街地を解消した。
- 旧法の中心市街地活性化基本計画を策定し、導入しているが、改正法の基本計画を作るべきかどうか、作って認定されるかどうか等、悩ましい問題があり、検討中である。
- まちづくりというこという言葉を使っているが、ハードはお金があれば、必要な土地をあければいくらでも出来るが、本当のまちづくりは、やはりソフトの面が入ってこそまちづくりと考えるので、ここ1、2年でハード面が完成するので、今後は本物のまちづくりをやって行かなくてはならない。そのため、商店主・地主・町内会長等のメンバーで地元にまちづくり協議会という組織を作ってもらい、これからの本当のまちづくりをどうしていけば良いかを検討していただきます。その中で、検討し、勝川のまちが発展するように我々も努力していきたい。
|
| (記録:古市博之/玉野総合コンサルタント株式会社) |
 (2)大正ロマン溢れるまち―彦根市四番町スクェアの取り組み (2)大正ロマン溢れるまち―彦根市四番町スクェアの取り組み
彦根市本町土地区画整理組合・彦根市本町地区共同整備事業組合
理事長 西村武臣氏
|
|
四番町スクェアは、彦根城下の夢京橋キャッスルロードの南に位置しています。かつてはアーケードのある一般的な商店街でしたが、ある時、一瞬にして空き店舗が増えました。当初は再開発事業の検討をしていましたが、平成8年に再開発事業を断念。しかし、このままではいけないと、商店街の若い人が「檄の会」という会を結成しました。対象は約80店舗。
檄の会では、自分たちでできることはないかとアンケートを実施。また、1人ずつ面接聞き取りも行い、「こんなまちには人が来ない。何とかしなければ。」という想いを強く持ちました。そして、1.3haと小規模ですが、当初は敷地整序型土地区画整理事業、後にまち中再生土地区画整理事業を行うことにしました。
一方、土地区画整理事業は基本的には個人の土地の整理を行うもので、共同で使う空間の整備はできません。そこで、区画整理事業と同じメンバー全員で、任意の組合の「共同整備事業組合」を立ち上げ、建物移転補償費の1割を出資し、その費用で共同利用する空間の整備を行いました。金額は1億6千万円でした。
また、土地区画整理事業の換地は、照応の原則があります。しかし、私たちはこれを全く度外視し、すべて飛び換地としました。どこでも「良い場所」となるよう、中央にパティオを設け、どこからでも入れるよう、また、角地が多くなるように計画しました。公共の道路以外の「路地」は、組合で買収しました。
完成後、㈱四番町スクェアという会社を設立。共同整備事業組合が任意団体であったこともあって、資金の管理上も個人名儀となっていたため、当初残った7千万円を出資した会社としました。
景観整備では、まちづくり協定をルールブックとしてまとめました。ある設計者を「マスターアーキテクト」として、このまちのあるべき姿をパースと模型で示してもらいました。
講演終了後の質疑
<質疑>このプロジェクトを通して専門家の役割はどのようでしたか。
<回答>特に専門家には入ってもらっていません。すべて自分たちで考えるということを基本にやってきました。
<質疑>まちづくりルールはどのように合意をとりましたか。
<回答>内容は、多くの方が納得できる、できるだけやさしいものとしました。
|
| (記録:今村敏雄/(株)連空間設計) |
■講演
 都市再生を図るイマジニアリング〜開発のデザイン手法について 都市再生を図るイマジニアリング〜開発のデザイン手法について
三上訓顯氏(名古屋市立大学大学院 芸術工学研究科 教授)
|
本日の講演は、イマジニアリングというものを縦軸とし、横軸としてシンポジウムのテーマであるコンパクトシティをクロスさせてお話をしようと思います。
●イマジニアリング(imagineering)
イマジニアリングという言葉は、イマジネーションとエンジニアリングを合わせた造語です。ディズニーカンパニーの一部門としてディズニー・イマジニアリング社という会社が実在し、テーマパークや地域開発をはじめとする企画やデザインを行っています。
これまでの工学的なことばかりではなく、イメージをどのように具現化していくかというクリエイティブな内容を綴っている言葉と思っています。
●Theory 〜アーバンデザイン理論におけるイマジニアリング〜
アーバンデザインの動向は、70年代までのモダニズム、70年代〜90年代のアーバニズム、そして90年代以降のニューアーバニズムがあります。モダニズムの時代というのは、建築技術を都市に応用することでひとつの将来イメージを書いていくことでありました。一方、アーバニズムというのは、従来あったものを否定するのではなく、それに付加したり還元したりして展開することかと思います。
『サスティナブル開発』
持続可能な開発は、経済成長の持続、市場経済の最大化、私的利潤の最大化、コスト削減などによる“経済の開発”と自立地域の増大、基本的人権の充足、公平・参加・アカウンタビリティの保証などによる“コミュニティの開発”、そして持続可能な環境容量の反映、資源保全とリサイクルの促進、廃棄物の低減などによる“エコロジカルな開発”の3つの開発が互いに共存、共棲することが必要です。
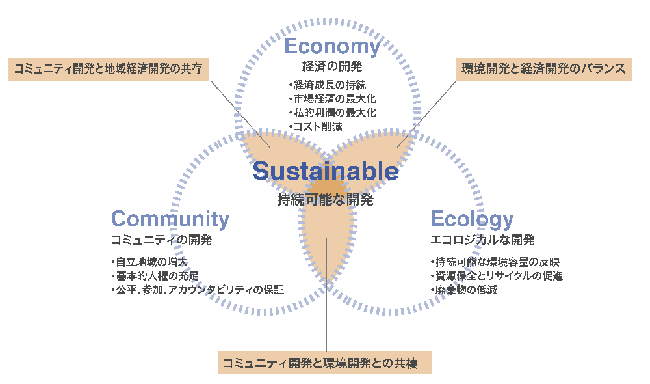
『コンパクトシティ』
持続可能な開発理念を実現してゆくための具体的方法がコンパクトシティの考え方あり、コンパクトシティの形成にはこのような原則があると考えている。
① 都市形態のコンパクトさ
② 複合用途と適正な街路システム
③ 自動車に過度の依存をしない強力な交通システム
④ 環境のコントロール
⑤ 暮らしの質や持続可能な都市経営
『シャレット』
シャレットとは、特定の目標に向けて全関係者が集まり、1週間程度でビジョンや構想などを具現化し、意志決定をしてゆくための、デザインワークショップになるかと思います。当然、シャレットを行う前には、住民の意見などは集約されていますが、2〜3日目でラフ図を描きギャラリーに展示することで、フィードバックが繰り返されます。5〜6日に目になると、ある程度のプランの方向性が確立されます。
●Practice 〜イマジニアリングの実践〜
高密度な開発と形成に最もあてはまる実例が、高城壁に囲まれた中世の都市です。相応に都市を防衛するのには、予想された外壁長の周長を最小限度に押さえる必要があった。その結果、都市の中にますますコンパクトに納まることとなり、かつまた相対的に密度を高くすることも生じ、行政、商業、住宅用途の一体化も必要となりました。

①囲郭型のコンパクトシティ(通商産業省 1989年提案)
- 異種機能を導入することで、単一機能の都市では味わえない魅力やメリットを生みだす
- 様々な都市コミュニティの活動の節点として“界隈”をつくる
- 街区全体が建物の室の中にいるようなポジティブな空間とする
②低容積仮設型コンパクト街区 (青森市 1995年提案)
- コンパクトな中に住宅やパブリック機能、ミュージアム機能、商業機能を詰め込み、ねぶた祭りの舞台としてゆけば良いのではないかという提案です。
- 青森市でコンパクトシティを目指す理由として、除雪、廃雪があります。これに係る費用が大きく、コンパクトな都市を形成することで行政サービスの効率化につながるからです。
③テーマ型コンパクトシティ (名古屋市 1998年提案)
- 1街区もしくは2街区を想定した、テーマ型のコンパクトシティの提案です。
- 街区の中に、マーチャン・ダイジングで出てきたアイディアを空間の骨格を考えながら言葉でおいてゆき(言葉の設計図)、これをもとにパタンパースを描きました。
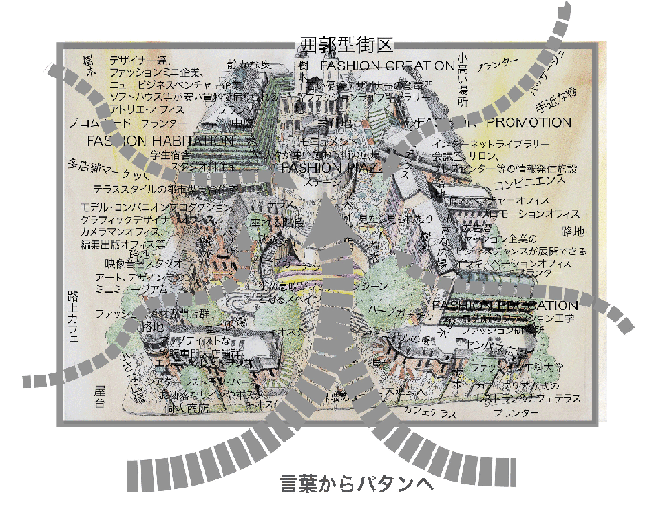
●人材育成におけるイマジニアリング教育 〜「ヴァーチャル・アイランド」プログラム〜
イマジニアリングの実践を通じてどのように人材を育成するかということですが、日本の大学のカリキュラムにはありません。そこで、人材育成のために「ヴァーチャル・アイランド」プログラムを作り、大学で使ったり、企業の研修で使ったりしています。
『ヴァーチャル・アイランド プログラム』
- PC上に人口の島を作成し、地球の緯度・経度を設定します。こうすることでヴァーチャルな島ですが、地域の特性を反映させることができます。
- しかし、ヴァーチャルな島なので地形図がありませんので、地形図を作成することとなります。地形図には、緯度・経度に従った風土や等高線を解読しながら、集落、土地利用、海洋利用、道路、史跡などの位置をプロットします。
- 島というのはある意味ではコンパクトシティと似ているわけですが、そのなかでどのように島を活性化させるのかという整備コンセプトを考え、マスタープランを設定します。
- 次に、ヴァーチャル・アイランドのマスタープランで設定した整備地域の中から1つを選び、この地区計画あるいは核となる施設を提案します。
- 最後に、ヴァーチャル・アイランドの地区計画あるいは核となる施設の提案をスケマティックデザインで表現することとなります。
●Proposal 〜コンパクトシティの提案〜
コンパクトシティ実現に向けては、郊外に住む人が都心に向かう際に公共交通に乗り換える場としてローカルハブを設置することと都心をどのように活性化させるかという2つの課題があります。
『ローカルハブ』
①ダイレクト・ジャンクション・タイプ
…駐車場を降りると即駅のコンコースにつながるタイプ
②インダイレクト・ジャンクション・タイプ
…駐車場と駅とが離れており、その間に公共公益施設や商業界隈、アメニティを配置するタイプ
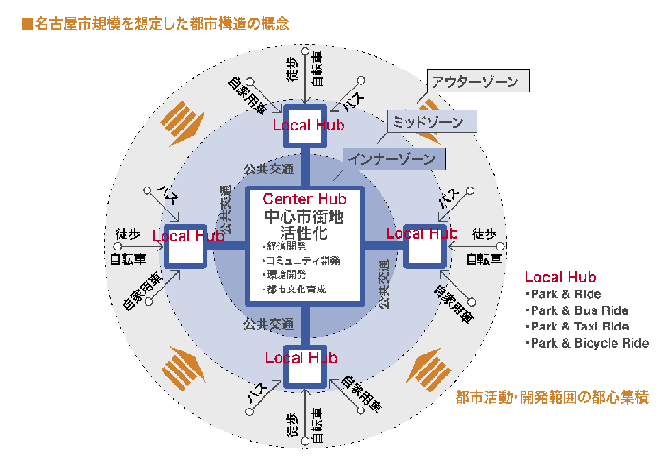
『センターハブ』〜笹島地区アジア経済特区構想立地概念〜
- 外資融資やアジア系企業の進出による金融を始め、貿易、製造業、流通、IT関連業などの経済機能を集約した、金融経済特区を都市規模で設置し、政府が制度面支援をしてゆく構想。進出企業には、税の軽減・低金利の融資制度・助成金など、企業の競争力を高めるための優遇措置、投資に対する特別なプレミアムをつけ、外資の誘致を想定する。

●まとめ
- 従来の都市再生では、世帯当たりの居住面積など定量的な説得が有効であったが、コンパクトな空間に人が集まる魅力は狭さの魅力を表現しないといけないので、定性的な説得方法が有効であると考えます。定性的な視点から心に訴える方法。それが、イマジニアリングであります。
- イマジニアリングの方法として「情報共有とコラボレーションツールとしてのシャレット」「言葉をイメージに変換するスケマティック・デザイン」そして「ヴァーチャル空間によるイメージ・シュミレーション」を紹介しました。
- 持続可能な都市とは、今後に予想される国際競争、開発途上国の経済発展、都市間競争下において、環境負荷を低減しながら、将来の利益や要求を充足する能力を継続的に維持しようとする戦略を持ち実践努力を行っている都市である。
|
| (記録:木下 博貴/(株)地域計画建築研究所 名古屋事務所 ) |
|
<主催>愛知住まい・まちづくりコンサルタント協議会
<共催>(財)名古屋都市センター
<後援>愛知県、名古屋市 |