|
愛知住まい・まちづくりコンサルタント協議会・2005年度公開シンポジウム
2007年問題とまちづくり
-団塊世代の大量退職がまちづくりをどう変えるか-
【日時】 2005年12月8日(木)13:30~16:30
【場所】(財)名古屋都市センター 11階大研修室
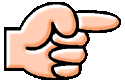 案内ちらしはここ 案内ちらしはここ
|

|
■次 第
1.永柳代表あいさつ
2.基調講演
「2007年問題が地域社会におよぼす影響」
講師 樋口美雄氏(慶応義塾大学商学部教授/
財務省財務総合政策研究所・「団塊世代の退職と日本経済に
関する研究会」座長)
3.まちづくりの担い手育成の取組みの事例報告
(1)まちづくりブックの取組み
報告 桑名市都市整備部都市計画課 久保康司氏
(2)まちづくりの根っこ探し-日進一歩-の取組み
報告 日進市都市建設部まちづくり推進課 宮地勝志氏
4.パネルディスカッション
「2007年問題をまちづくりの好機としてとらえる」
○コーディネーター
今村敏雄 (愛知住まい・まちづくりコンサルタント協議会運営委員/
(株)連空間設計代表取締役)
○パネラー
佐藤允孝氏(揚輝荘の会事務局長)
中井保三氏(大高まちづくり協議会/なごや環境大学)
久保康司氏(前掲)
宮地勝志氏(前掲)
○コメンテーター
樋口美雄氏(前掲)
|

永柳代表 |
■講演
「2007年問題が地域社会におよぼす影響」
樋口美雄氏(慶応義塾大学商学部教授/財務省財務総合政策研究所・
「団塊世代の退職と日本経済に関する研究会」座長)
|
- 従来は、国が公共事業などで地域の雇用を作り出してきたが、今後は地域の実力で雇用を作り出していく必要があり、地域間格差は広がることになる。
- 地域のリーダーとなるべき人を上手く育て、能力を発揮させるとまちは発展する。
- EUの中ではデンマーク、オランダ、アイルランドの3国が優等生だと言われ、オランダは13%あった失業率を2.5%に改善している。
- フランスは手厚い失業保険給付制度により失業者という職業を生み出したと言われるほど、失業率が悪化している。
- 技術革新が繰り返される中、そのスピードに対応できる人づくりが重要である。
- アメリカやカナダは移民を積極的に受け入れ、デンマークは育てることを重視している。
- 日本全国が能力開発へのコストや人件費の削減を行っている中、人づくりを大事にしていた東海地方はいち早く景気が回復した。
- 性別による役割分担が明確な国に出生率の低下が見られ、これは女性が就業する社会になっていないことを示している。
- 世界に先駆けて人口減少が始まる日本は世界からその対応が注目されている。
- 日本は1947~49年の3年間という非常に短いベビーブームであり、団塊と呼ばれた世代は常に社会に影響を与え続けてきた。
- アメリカでは定年制度は年齢差別のひとつであり憲法違反にあたるとして禁止されているが、能力や意欲によって解雇することが認められている。
- アメリカでは63歳で引退する場合に最も有利な年金制度になっているため、65歳の年金支給までボランティアやNPOで働く人が多い。
- 団塊世代の引退によって貯蓄率が低下するため税制改革が必要になる。
- 集団就職した団塊世代の次の世代が少ないため、技術の継承が行われないのが問題。
- 定年後の行動選択について、遊ぶことと仕事だけではなく地域への参加という新たな選択が生まれてくる。
- まちづくりに関して日本は官と民で2分化しているが、アメリカやカナダのように中間組織を作ることが必要。
- 今後グローバリゼーションが進む中、ローカリゼーションがますます重要になってくる。
|
 |
| (記録:山崎崇/(株)都市研究所スペーシア) |
■まちづくりの担い手育成の取組みの事例報告
(1)まちづくりブックの取組み
桑名市都市整備部都市計画課 久保康司氏
|
- 桑名市で作成したまちづくりの入門書「まちづくり極意 くわな流」とその取組みについて紹介する。
- 桑名は長い歴史と文化を持つ水郷のまちである。城下町、宿場町、そして港町という多様な性格を持ちながら栄えてきた。平成16年12月に隣接する多度町、長島町と合併し、14万人都市となった。
- 桑名には旧城下町の昔からの住民とニュータウンの住民がいるが、それぞれに桑名の歴史、文化とそれぞれのまちを知ってもらい、両住民が一体となったまちづくりが進められるよう「まちづくり極意くわな流」を作成した。
- 作成に際して委員会を立ち上げ、公募により郷土史家、建築家、会社員などの市民が委員として参加したほか、市民活動を行っている市民にも要所要所で協力していただいた。
- 2000年末頃から委員会を開催。夕方7時頃から桑名駅終電の11時頃まで、何十回という議論を重ね、同時にまちを歩いたりしながら作成した。途中で試読会も開催し市民からの意見も聞いた。
- 本の付録として桑名に伝わる千羽鶴を折る紙を付け、文化に触れていただけるよう工夫している。また小学校高学年から読めるよう、イラスト、写真を随所に入れた。
- 本は序章と第1章から5章までによって構成されている。序章では空から見た桑名を紹介し、1章から3章までは桑名の人々の生活ぶりや歴史、文化、まちづくりの取り組みなどを紹介している。
- 第4章では、まちづくりの極意は市民の力であるとし、続く5章において、簡単に取り組むことのできるまちを知る術を手ほどきしている。
- この本を使った取り組みであるが、編集委員会のメンバーによって「蛤倶楽部」が新たに立上げられ、今年度二つの講座に取り組んだ。
- 一つは小学生を対象にした「調べる学習」おたすけ隊というもので、桑名のまちの不思議を調べることによって、子どもたちにこれからの桑名のまちづくりの担い手として育っていただきたいという願いから開催した。
- もう一つは高校生以上を対象に、残したい街並みをスケッチしてもらう講座を行った。スケッチする対象を選び、描くということは、街の好きなところを見つけ、観察することにつながり、街を考えるきっかけになると思われる。蛤倶楽部では以上のような2つの取り組みを行った。
|
 |
| (記録:福井秀樹/(株)地域計画建築研究所 名古屋事務所) |
(2)まちづくりの根っこ探し-日進一歩-の取組み
日進市都市建設部まちづくり推進課 宮地勝志氏
|
- 日進市は人口が急増し、公共投資による財政逼迫の問題や、建築や開発のトラブルが増えてきた。それらを規制誘導するために「まちづくり条例」の必要性が高まったのが発端。
- 座・まちづくり塾「日進一歩」は、市民が主体となった自治基本条例づくり、開発等事業に関する手続き条例づくりのための、素地づくり・素材集めのひとつのチャンネルとして始まった。
- 自治基本条例は、国とは独立して自治体にも行政権が市民から信託されているという二元信託論にもとづく"自治体の憲法"というべき重要な条例。「そのまちとしての価値」がこめられていなければならない。平たく言うと「日進らしさ」「日進流」を見つけるために、幅広い話題で市民参加の機会を作ってきたのが「座・まちづくり塾 日進一歩」。
- 「日進一歩」のスタートは「寺子屋おはなし会」シリーズとして8回、高田弘子さん、吉田一平さんなどの講師を招いてお話を聞き、意見交換した。次は「道」シリーズとして3回、街道筋の歴史を学び、フィールドワークをした。そして「川」シリーズを3回、「山」シリーズを3回、フィールドワークを中心に開催した。
- 「日進一歩」は計17回開催し、その後は条例検討会を80回、延べ900人の市民参加で検討され、まさに今日、市長へ提言する日を迎えた。
- 最後に「開発等事業に関する手続き条例」について。従来の要綱による行政指導に限界があり、トラブルを未然に防止するため、事業者が住民に説明する手続き、住民からの意見表明の手続き、開発等事業と土地利用計画との整合を図る仕組みを規定したもの。その中で特徴的なのが「地区街づくり計画」制度です。街づくり協議会、準備会、計画づくりの方法、街づくり協定について定めている。「参加」の時代から「協働」の時代へ向けた自治の仕組みづくりとなっている。
|
 |
| (記録:藤森幹人/ (株)日建設計 名古屋) |
■パネルディスカッション 「2007年問題をまちづくりの好機としてとらえる」
○コーディネーター
今村敏雄氏(愛知住まい・まちづくりコンサルタント協議会運営委員/
(株)連空間設計代表取締役)
○パネラー
佐藤允孝氏(揚輝荘の会事務局長)
中井保三氏(大高まちづくり協議会/なごや環境大学)
久保康司氏(前掲)
宮地勝志氏(前掲)
○コメンテーター
樋口美雄氏(前掲) |
|

|
| 今村氏 |
- 樋口先生からは、グローバルな視点から2007年問題の話をいただいた。桑名、日進については、まちづくりを担当する市職員から、市民参画・協働の話をいただいた。
- まずは、佐藤さん、中井さんに定年退職後の活動状況を伺いたい。
|
| 佐藤氏 |
- 私は団塊の世代の一世代前の人間。
- 揚輝荘の会は、松坂屋の創業者の別荘として建てられた揚輝荘をまちづくり活動の資源とできるのではないかと考えて、取り組んでいる。
- 生涯学習研究会・なごやでは、生涯学習を行いたい人の初めの一歩の相談に乗っている。団塊世代の方にも生涯学習の世界に入っていただけるよう、団塊世代対象の講座を考えている。
|
| 中井氏 |
- 49年生まれの団塊の世代で、2004年の4月に早期退職をして今は無職。
- 大高まちづくり協議会ではホームページの編集を担当している。また、なごや環境大学にも参画している。
- 団塊の世代はアナログとデジタルの両方を知る世代で、会社で培った知識や技術があるので、今後、何かの役に立つと思う。私くらいのスキルの人間は、愛知県にあふれ出てくるので、その人たちがまちづくりに関われば大きな力になる。
|
| 今村氏 |
- お二人とも活動量は多い。中井さんを始め、私も団塊の世代だが、地域に帰る中で、まちづくりブックを活用するようなことについて話を聞かせていただきたい。
|
| 久保氏 |
- 知識や経験をもった方が、まちづくりブックの委員になっていただけるとよい。そういう委員会があることを生涯学習の会などを通じて案内してもらえるとよい。
|
| 宮地氏 |
- 団塊の世代の方には好きなことをやっていただければよいのではないか。団塊の世代の活用というのは失礼だと思う。あまり行政から口を出すのもよくないと思う。
|
| 今村氏 |
- 団塊の世代の先輩として、退職前の仕事と今の活動の関係をお話しいただきたい。
|
| 佐藤氏 |
- 退職前は人事部で、セカンドライフの社内研修をしていた。自分も生きがいづくりをしなくてはと思い、大学での学芸員の資格取得、揚輝荘の会、生涯学習の活動へとつながった。
- 生涯学習の相談では、最近は、趣味を楽しむというより、習ったことを社会に役立てたいと考える人が増えてきており、まちづくりには追い風という気がする。
- 団塊の世代は生涯学習の入り口のところで迷っている。趣味から一歩進めて、まちづくりなどにまで取り組んでいただきたいと思う。
|
| 樋口氏 |
- うまくいっている地域はどういうところなのか考えてみると、過去の経験などに裏付けられたリーダーの存在がある。行政の中でも市民でも、退職を迎えた人でもよい。愛知県はそういう人材が多いと感じた。
- (地域の活動などに)後から入ってくる人に対して、受け入れる側、入ってくる側ともに意識をかえないといけない。
- 高齢者のニート問題もある。若者と同じで、生涯学習など相談にきてくれればしめたものだが、出てこない人をどうするかも問題。
|
|
(記録:今村洋一/㈱UFJ総合研究所) |
|
|
<主催>愛知住まい・まちづくりコンサルタント協議会
<後援>愛知県、名古屋市 |