|
愛知住まい・まちづくり協議会2005年度2月交流会
日本アートマネジメント学会中部部会第13回研究会
実践!! アートマネジメントのまちづくり
〜アートをまちづくりに生かすには〜

■日時 2006年2月28日(火) 18:30〜21:00
■会場 名古屋都市センター 第3・4会議室
■報告者 川本直義氏((株)エルイー創造研究所 取締役主任研究員)
星野 博氏(NPO法人志民連いちのみや 理事長)
■参加者 32名
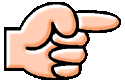 案内ちらしはここ 案内ちらしはここ
|
■事例報告1
「やまのて音楽祭 ほか」
川本直義氏
|
やまのて音楽祭実施の経緯
 やまのて音楽祭は、名古屋市の新世紀計画2010で城山・覚王山地区の資源を生かしたまちづくりが謳われていたことから、平成12年に行政主導で始まった。エルイー創造研究所は当初からコーディネート役として関わっている。 やまのて音楽祭は、名古屋市の新世紀計画2010で城山・覚王山地区の資源を生かしたまちづくりが謳われていたことから、平成12年に行政主導で始まった。エルイー創造研究所は当初からコーディネート役として関わっている。
城山・覚王山地区魅力アップ事業実行委員会が立ち上がった当初は、「歴史を生かしたまちづくり」として史跡散策や建物の見学会、マップづくりを行っていたが、イベントごとに音楽を少しずつ取り入れる工夫をしていった。
平成14年に変化が起こった。それまで熱心に取り組んでいた区役所の担当者が異動となり、これを機に実行委員会がより自主的な活動をしていくこととなった。実行委員会全体をワーキンググループ(分科会)に分け、この分科会レベルでの会議は基本的に行政抜きで行うようになった。また、ワーキンググループ制にしたことにより、全体をつなぐ総合的な企画が必要だということで、音楽祭の実施が発案された。ここで重要なのは、実行委員の中から自発的な発案が出てくるのを待つことであった。行政やコンサルがはじめから「音楽祭をやりませんか?」と持ちかけたら、うまくいかなかっただろう。
どうやって音楽祭をやるか?
それまでイベントごとに音楽の演奏を取り入れてきたこともあり、ある程度は自分たちでやれるという実感が実行委員のメンバーにもあったのは、大きなプラス要素だった。
しかし、資金も専門家(人材)もまったくゼロの状態では、実際に音楽祭の仕組みをつくることが難しい。そこで、名古屋芸術大学の竹本先生をはじめ、アートマネジメントの専門家にアドバイスを求めたことも重要なポイントだった。
やまのて音楽祭の実施
やまのて音楽祭を実施するにあたり、以下の方針のもとに行った。
(1)実行委員は公募で集め、誰でも入れる開かれた組織とした。結果、集まった実行委員たちが、自由な発想で様々な企画を行う環境ができた。
(2)実行委員の中だけでやろうとせず、様々な団体の協力を得ることが大切。やまのて音楽祭では、各コンサートをできるだけ市民団体で受け持ってもらう方式をとっている。
(3)音楽祭のパンフレットとまちづくり情報誌とをドッキングさせたことも工夫の一つ。まちづくり情報誌を作ってもいつも同じ人たちしか読んでくれない、置いておいても持ち帰ってくれないという悩みがあったが、こうすることで必然的にコンサートに来た人たちの手に情報が渡ることとなる。
(4)様々な仕事を作ることが重要。公募で集まった実行委員が有能感、有効感を感じるように工夫する。
音楽祭を実施した結果、今まで高齢者が多かった史跡散策などと比べ、幅広い年齢層が参加したという成果があった。また、まちづくりの中での音楽祭であるということで、いろんな団体、個人の新たな協力関係が作られたのも大きな成果だった。
また、このような音楽祭の実施が、次なる展開へと結びついていることが重要なポイントである。昨年秋から、この地区を文化の里と名付けてアピールしてはどうか、という構想が自発的に生まれ、秋に文化的なイベントがないということで、秋にお茶をテーマにした「お茶めぐり、まちめぐり」というイベントを開催した。
以上
|
■事例報告2
「まつりづくりがまちづくり」
星野 博氏
|
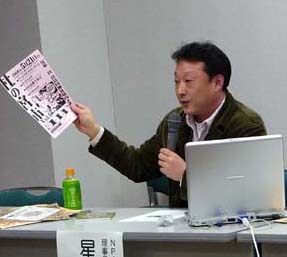 自分たちの活動では、意識的に「イベント」という言葉は使わず、「まつり」と言う。 自分たちの活動では、意識的に「イベント」という言葉は使わず、「まつり」と言う。
「まつり」とは、表現の場であり、「まつりづくり」とは、そうした表現のための舞台をつくることである。
一宮市は、以前は産業が盛んで華やかな時期もあったが、現在では駅前の商店街も空き店舗が目立ち、さみしい状況。これからは、「フツーのまち、いちのみや」として、持てるまちから持たないまちへと、自分たちの認識も変えて行かなくてはいけない。そんなフツーのまちで、何をしたら幸せになれるのか?小さいが雑多な活動を自己責任で個々がおこなっているまち、それが楽しいまち、未来に繋がるまちなのではないかと考えている。
杜の宮市が始まった経緯
毎年開催される一宮七夕まつりは、来場者が130万人と言われている。この大きなまつりの中で、小さなまつりづくりをしようということで、「どすこいライブ」を始めた。これは真清田神社裏の大宮公園にある土俵の上でライブを行うもの。自分たちができることを自分たちで作っていくことが、「ドコデモダレデモな七夕まつり」であり、これが拡大したものが「ラブたな」(七夕まつりを愛する志民の会)である。市役所隣の公園に仮設した「にぎわい広場」で、ステージや特色ある飲食などを展開している。この中の「ラブTワークス」という企画で、それぞれの人がろうけつ染めをしたTシャツ138枚を集めた。これが、個々の人が違うことをやりながら、どこかでつながっている、という目指すまちの姿を象徴している。
そんな中、真清田神社から、神社で文化的な催しをやってくれないか、という話があった。一宮市のまちの興りとなった、神社前の三八市を、文化的な手法で復元できないだろうか、と考えたのが杜の宮市の始まりだった。とはいえ、何もない状態からのスタートだった。明確な企画内容さえも決めなかった。公募でスタッフを募集し、100人近くが集まったが、何もないところからスタートして企画内容を話し合いましょうと言ったら、来なくなった人が半分近くいた。それでも残った人たちで何度も話し合ううちに、アート&クラフト、特色ある飲食、市民活動団体の紹介という内容に集約していった。
杜の宮市の目指すもの
杜の宮市の来場者は1日で約1万人。ライブ50組、全国からのアート&クラフト100組、飲食ブース20店、市民活動大集合、トークライブなどを行う。
学生の頃の学園祭のワクワク感、エネルギーを取り戻すことができないか。そういうときこそ活躍するような生徒がいたが、まちにそんな人がたくさん眠っているのではないか。彼らの活躍する場がなく、抑えつけられているのではないだろうか。そんな思いから、まつり=「ハレ」の場づくりとして杜の宮市をやってきた。生活空間の中で、自己責任で自発的に活動する「志民」を造っていきたい。
その他、いくつかの空き店舗を1日だけギャラリーとして使用し、ラリーを行った「今・店舗・ラリー」(コンテンポラリー)、店主が日替わりで変わることで、空間の時間的なシェアを実現した「三八屋」などの試みも行っているが、まちに隠れた力を発掘したり、個々のネットワークがつながっていったりなどの成果があった。
さらに新たなまつりづくりへ
杜の宮市をやっていく中で、1日だけ盛り上がった後は、いつもの毎日に戻ってしまうことに疑問を持つようになった。残りの364日は何もなくてもいいのだろうか。1日のみの大きなまつりではなくて、日常の小さなまつりを同時多発化させられないだろうかと考えた。
一つの大きなまつりよりも、小さなたくさんのまつりが集まれば、より大きなコミュニケーションの場ができるのではないだろうか。これこそ、「ドコデモダレデモなまつりづくり」だ。小さなことなら、思いさえあれば誰でも、自分の家でもできる。これをネットワークでつないでいけば、それぞれが自分の居場所が見つけることができる。こうした考えから、「三八サンデーいちのみや」が始まった。3と8が付く日曜日に、それぞれが小さなおまつりをやりましょう、というものだ。
まとめ
素人が活動をしていく上でのいい点は、素人だから、失敗してもなんてことはないということだ。「ごめんなさい!」と謝ればよい。失敗をおそれずにどんどんトライできるのは強みである。これを「失敗力」と呼んでいる。
失敗を恐れず、自分の責任で自分の思いを行動に移す、そんな「志」を持った「志民」の力「志民力」を集めていきたい。
以上
|
■全体討議
|
| 発言者1: |
まちづくりの活動の中で、市民と住民(まさにその地域に住んでいる人たち)、趣味の人(そこでなんらか自分の表現がしたい人たち)という、大きく分けると3種類の人たちが関わってくるが、いつも住民が抜け落ちてしまうことを心配している。そのあたりは、どのようにされているのか? |
| 川本: |
住民だけでやろうとすると苦しいし、行政から依頼されると義務的にもなる。もっと立場をフラットにして、広くスタッフを募集した。外の人を入れることで、地域の人も動くのではないか。 |
| 星野: |
中心市街地の団体の人たちとはあまりうまくやれていない。どちらかといえば「根なし草」のような存在。一生懸命やるほどに、地域の人は「あいつらは特殊だ」となる。いろいろなアプローチもしたが、地域の人が変わっていくことも必要だと考え、長い目で見ることにしている。 |
| 川本: |
行政の役割というのも大きい。行政と一緒にやっているということでお墨付きがあるので、安心して参加してもらえるという部分。 |
| 星野: |
実際にはなにかバックアップがあるといいとは思っている。が、行政はお墨付きを与えると今度は自分たちが責められてしまうということで、臆病になってしまっている。そのあたりから解決していくべきではないか。 |
| 発言者2: |
木曽川町の会館の検討に関わっていたが、一宮にこんな素晴らしい活動があるとは知らなかった。行政も市民のニーズを満たそうと頑張っており、市民は市民で自分のまちのために一生懸命に活動している。お互い考えていることは案外似ているかもしれないが、それをつなぐ何か、誰かが足りないだけではないか。きっとそんなに難しいことではないと思う。 |
| 発言者3: |
行政の立場から見ると、行政をうまく動かせていない感じがする。
総合計画の中に謳われているプロジェクトの一部を手伝いますよ、という提案をするならば、行政マンは話に乗ってくるだろうし、予算も取ってくる。 |
| (記録:花村珠美(エルイー創造研究所)) |
|
|

 やまのて音楽祭は、名古屋市の新世紀計画2010で城山・覚王山地区の資源を生かしたまちづくりが謳われていたことから、平成12年に行政主導で始まった。エルイー創造研究所は当初からコーディネート役として関わっている。
やまのて音楽祭は、名古屋市の新世紀計画2010で城山・覚王山地区の資源を生かしたまちづくりが謳われていたことから、平成12年に行政主導で始まった。エルイー創造研究所は当初からコーディネート役として関わっている。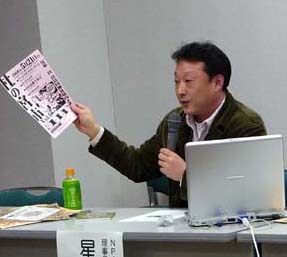 自分たちの活動では、意識的に「イベント」という言葉は使わず、「まつり」と言う。
自分たちの活動では、意識的に「イベント」という言葉は使わず、「まつり」と言う。