Aグループ要約(菅野)
|
|
 グループワーク写真 |
 グループの発表写真 |
Bグループ要約(有我)
松坂屋といえば、名古屋に根ざしている百貨店であり、その創家の別荘である陽輝荘は市民にとって親しみが感じられるものである。また、陽輝荘は名古屋の中心部にありながら、豊かな緑に囲まれた品格が感じられる空間であり、地域住民にとっては、一度は入ってみたいと思う敷居が高い存在でもある。 |
|
 グループワーク写真 |
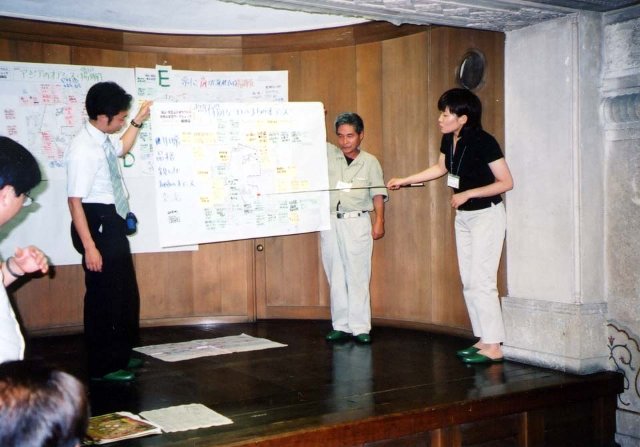 グループの発表写真 |
Cグループ要約(池田)
揚輝荘を訪れる全ての人に、さながらデパートのように、楽しくて多様な「自然を体験し歴史を発見する」空間や機会を提供したいと考え、以下のようなキーワードや具体的な機能を出し合った。
|
|
 グループワーク写真 |
 グループの発表写真 |
Dグループ要約(今村)
松坂屋の創始者である伊藤家が名古屋で育んできた文化とアジア各国の学生との交流を意識されている人が多く、その方向で活用を図りたいという意見が多く出された。また、都会である名古屋の中にあって、貴重な緑のオープンスペースとなっていることから、地元に住む人にとって、心身共に癒されるオアシスであるという認識も強かった。そこで、地元の人とアジアの人が活発に交流し、互いの文化にふれ合う場としての活用が志向された。さらに、伴華楼は茶道・華道などの教養美、庭は日本庭園としての庭園美と緑の繁る自然美、聴松閣はおもてなしの心、日本人の美しい心といったように、昔のような美が失われつつある現代にあって、様々な美に触れることのできる貴重な場所としての意味も付加されたアジアのオアシスになってほしいという思いもあり、そして、そこに集まるすべての人には陽気に過ごしてほしいという願いが込められたアイデアとしてまとめられた。 |
|
 グループワーク写真 |
 グループの発表写真 |
Eグループ要約(竹内)
Eチームは8名のメンバーのうち、揚輝荘に初めて入った人が4名と、どのチームよりもフレッシュな感覚でのスタートとなった。実際に目で見た、庭園の圧倒的な緑のイメージは強く、その庭で誰に何をさせたいか、そしてWSの会場である聴松閣をどう活用するか、その二点に意見は集中した。そして日本庭園のゾーンと聴松閣ゾーンのそれぞれを考えながらも、万人にわかりやすい共通のテーマが求められた。 |
|
 グループワーク写真 |
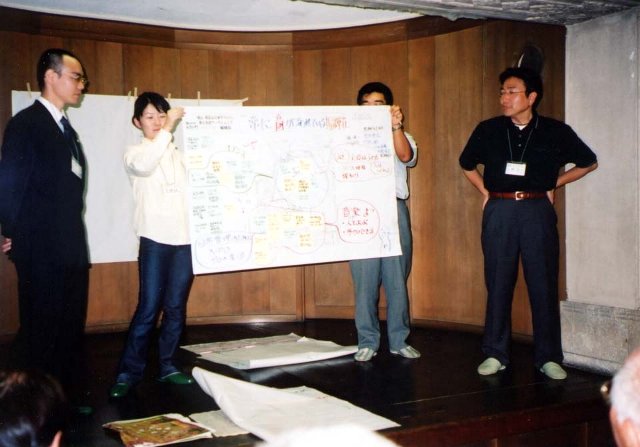 グループの発表写真 |
|
各グループが成果を全員の前で発表した後で、鈴木先生の進行で全員による意見交換が行われました。 「品格」を保ちながらも「親しみ」のある施設に、活用しながら価値を高めていく活用法、といった難しい課題がだされ、参加者全員が真剣にその答えを探る意見交換会でした。 形の資産とともに、揚輝荘の持つ歴史性や物語性といった無形の価値もあわせて、多くの市民の心に受け継いでいくことが強く望まれていると感じました。 【意見交換会での主な意見】
|
|
 意見交換している写真 |
意見交換のまとめ板書 (クリックすると大きな画像がでます) |
| (全体記録:藤森 幹人/(株)日建設計名古屋オフィス) | |