◇ 記念講演 「環境と人にやさしい交通の未来像 ~都市交通を対象として~」
森 川 高 行 氏(名古屋大学大学院工学研究科教授)
● 「環境にやさしい」と「人にやさしい」は両立するか?
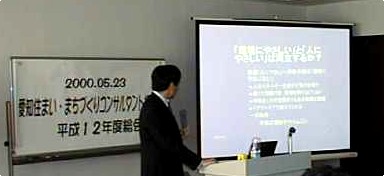 通常、「人にやさしい」移動手段は「環境にやさしくない」といえる。障害者や高齢者など全ての人にやさしいためには、①人のエネルギーを使わず動力を使い、②座って移動でき,荷物も持たなくてよい、③雨風をしのぎ空調までもある快適な空間(箱)、さらには④ドアツードアで運んでくれることが求められる。これで行くとその移動手段は、自動車を指し、究極は運転手付リムジンとなる。
通常、「人にやさしい」移動手段は「環境にやさしくない」といえる。障害者や高齢者など全ての人にやさしいためには、①人のエネルギーを使わず動力を使い、②座って移動でき,荷物も持たなくてよい、③雨風をしのぎ空調までもある快適な空間(箱)、さらには④ドアツードアで運んでくれることが求められる。これで行くとその移動手段は、自動車を指し、究極は運転手付リムジンとなる。
しかし、「人」を移動手段を利用する自分だけと考えなければ、周りの人にやさしいことも求められよう。そうなると、①公害を出さない、②事故に巻き込まない、③将来の人にやさしい(エネルギーを大量消費しない、温暖化ガスを排出しない)、④地域全体の人にやさしい、⑤まちづくりに貢献する、⑥障害者やビジターにもやさしいなどが必要条件となるだろう。そうすると、「これまでの自動車の使い方」ではないであろうということになる。
● Car-Dependentな街の問題
Car-Dependentな(自動車依存型)街とはどんな問題があるのか。まず、エネルギー・地球環境・地域環境の問題がある。日本では現在、CO2排出量の20%が車であり、欧米先進国では25~30%程度である。一方見方を変えると、平均的な3人家族のCO2排出量の1/3が車だといわれている。やはり車のエネルギー利用とCO2排出量は膨大であると分かる。また代表的な環境汚染物質と言われるNox、SPMの大半、3分の2が車からである。
渋滞問題もある。当然いわれているのが、道路整備だけでは絶対に解決できない。例えばLAでは片側5車線、合計10車線の立派な高速道路を整備したが、渋滞は全く緩和されなかった。
また土地利用の面から見れば、スプロール型の土地利用が進み、結果非常にメリハリのない開発が進む。それに伴い、都市インフラの非効率性が発生し、自然環境破壊も進む。またスプロール型の土地利用で最近大きな問題となっているのが、商業施設の郊外化であり、中心市街地の衰退や郊外大型店の進出/撤退の繰り返しが起こり、これらの郊外型商業施設の跡にはアスファルト化された広大な敷地が残り、まちづくりには全く貢献しない。最後に公共交通の衰退がある。車利用にシフトが進み、駅を中心とした日本型開発が衰退し、交通弱者やビジターの交通機会を奪うことになる。これは災害等の非常時にも弱いまちとなる。個人の利用が車にシフトしているのを見ると、個々人は車の非常に良い面を享受していると言えるが、まちづくりという側面から見ると、車社会にはこれらの問題点が浮上している。
● Car-Freeな街への軟着陸
 Car-Dependentな街の対極として、全く車を必要としないCar-Freeな街が考えられるが、ここまで依存してしまった以上、突然の変化は不可能であり、「軟着陸」を検討したい。散歩・ドライブなどは別として交通には必ず何らかの目的行動が存在する。つまり、交通問題は交通対策だけでは解決できず、土地利用やライフスタイルの変化との連動が重要である。職住近接の土地利用や、銀行などのサービス機関のオンライン化、あるいは週5日の通勤体制を4日にするなどの施策が考えられる。
Car-Dependentな街の対極として、全く車を必要としないCar-Freeな街が考えられるが、ここまで依存してしまった以上、突然の変化は不可能であり、「軟着陸」を検討したい。散歩・ドライブなどは別として交通には必ず何らかの目的行動が存在する。つまり、交通問題は交通対策だけでは解決できず、土地利用やライフスタイルの変化との連動が重要である。職住近接の土地利用や、銀行などのサービス機関のオンライン化、あるいは週5日の通勤体制を4日にするなどの施策が考えられる。
交通施設整備も土地利用の改変も大変な時間と費用と合意形成の手間がかかり,既存の施設を利用しながらの息の長い取組みが必要である。これはなかなか効果が見えず、市民には理解が得にくい。そこで、Sustainableでありながら明るい、街と生活と交通の未来の姿を市民に示し続けなければいけない。
この軟着陸の着陸先は、TDLやITSといった言葉が出てくるが、未来像として夢物語ではなく近未来に実現できるものを考えたい。一つは土地利用との連動であり、TOD
(Transit Oriented Development)がある。トランジットは公共交通機関とほぼ動議でありこれに基づいた都市開発である。1950年代からアメリカは高速道路に基づいた都市開発を進め、最近TODに切り替えているが、日本のまちづくりにとっては温故知新、ずっと進めてきており、成功している。しかし世界に先行して行ってきたのにも関わらず、それを忘れかけ、Highway
Oriented Developmentに向かっているのではないか。アメリカでは日本の民鉄型開発を参考に新しいTODを進めようとしている。代表的なものとしてはPortland等がある。(中部開発センター雑誌「Crec」に紹介)TODを見直すべきではあるが、鉄道沿線の地価が高いために自由競争では進みにくいという問題がある。また、人口減少時代を迎え,郊外の大規模開発の需要は少ない。これに対し、交通アセスメントを行い,交通利便性により、規制または税制を変えるなどの施策が必要である。オランダでは、ABC立地政策という、土地や土地利用主体をグループ分けしAの土地にAの主体、B土地にはBの主体を結びつけるというTODを行っている。
● 中心市街地のCar-Free化
Car-Free化ができるとすれば中心市街地であろう。まずは当然歩いて楽しいまちづくりが基本であり、再開発ビルや地下街に囲い込むよりも、道との接点を大切にすべきである。東京などでも臨海部に出来る人気スポットはほとんどが建物で囲った中に人工的な空間を作り上げており、道との一体性は見られない。オープンカフェなどの工夫が欲しい。また、車との交錯は最小に押さえ、空間的、時間的分離を検討したい。部分的にフルモール化し、その回りはハーフモール化するなどの施策が必要である。
中心市街地の活性化において留意すべき事は、土地利用を純化させすぎないことである。官庁街等に顕著に見られるが、単一的で働くにも楽しくないまちが広がっている。オフィスも飲み屋も混在したまちが望ましい。
歩くことが基本ではあるが、歩行に困難を感じる人がいたり、長距離の移動も考えられ、歩行支援手段が必要である。トランジットモールがある。一番恰好が良いのはLRTだが、ポートランドで見られるように無理にLRTを導入しなくてもバスでも工夫次第で魅力的になる。理想的には郊外電車と直結する事であるが、日本の場合突然には難しく、段階的な検討が必要である。
また、巡回バスも登場している。これもワンコイン化が望ましい。レンタル自転車やキックボードなども歩行者支援手段として十分、考えられる。マナーの問題があるが、広島等でレンタル自転車は始まっている。専用道や駐輪施設などそれなりの施設が必要になるが、名古屋では比較的作りやすいのではないか。貸し出しに関わる管理体制は、IT技術の進歩により、合理化できる。ただし自転車は乗れない人がいたり天候に左右されるという弱点がある。そこでレンタルエコカーを町中で貸し出してはどうか。
車対策をいくつか考えねばならない。法律も何も変えずに実現できる日本におけるロードプライシングは、違法駐車取締からといえる。違法駐車の取締を徹底すれば駐車場付置義務は不要であろう。また、中心市街地に幹線道路は不要である。現在の幅員構成から歩行者・トランジット系の比率を高めれば自ずと車の交通容量は低下する。結果的にまちはハーフモール化する。次に、要となる駐車場だが、休日には、駐車するために道路上に車が並んでしまう。道路の容量は減り、アイドリングにより環境にも悪影響である。周辺の駐車場は開いているわけだから、これをITSにより適切に誘導し、道路上の駐車場待ちも規制すべきである。
中心市街地における商業者はこういった駐車場の締め出しは、利用者を減少させるといって、いやがるが、目的を決めた買い物はあきらかに郊外店が有利であり、中心市街地こそ商業だけではなく、文化で勝負すべきである。文化は劇場や美術館だけではない。その街ならではの商品や食文化、買い物+観劇+飲食などの複合活動の受け皿としての魅力が重要である。また、歴史的遺産や都市景観は強力な文化的アトラクションであり、こういった文化で勝負すべきである。
● 街のCar-Free化は現実的か?
ごく限られた中心市街地の一部におけるCar-Free化は可能だがまち全体となると不可能だろう。まず消費者は車の利便性は捨てられない。時間的・空間的に定型な通勤交通以外をトランジットだけでサービスすることは不可能である。また、歩行困難者はどうするか、都市内物流はどうするかなど、課題は多い。街全体のCar-Free化が不可能ならば、車自体のグリーン化やIT・ITSの進展をにらみながら共存していく道を探ることが考えられる。Car-Less化の考え方である。トランジットの改善が必要であるが、幹線交通はかなりサービスが充実しているが、端末交通において不便であるという理由から車で都心まで出てくる人が多い。郊外部ではPark&Rideなどが進んでいるが、これも名古屋市内ではなかなか難しい。東京では民鉄との相互乗り入れ、営業時間の延長が進んでいる。公共交通は料金が高いという問題がある。独立採算的にやっていこうとするとやはり、鉄道の廃止、バス路線化となってしまう。少なくとも公営交通とそれと競合する民営交通部分には税金を投入すべきである。都市の装置あるいは市民の足としての位置付けが必要である。
次にTDMがあるが、ピーク分散策は渋滞対策でありCar-Less化にはならない。HOVレーンもバスレーンの有効活用としてはいいかもしれないが、Car-Less化政策としては日本では難しい。ロードプライシングは有効だが合意形成が難しい。車に対するペナルティを付けるよりもむしろ、保有や燃料に対する環境税の方が現実的である。駐車マネジメントはCar-Less化のためには有効と考えられる。
IT(Information Technology)の中身として、VICS(情報提供), ETC(自動料金収受システム)、
AHS(自動運転)の3本柱があるが、これら自体は車の効用を高めることとなり、Car-Less化にはつながらない。テレコミューティングのCar-Less化への効果は、買い物,医療,日常的な野暮用などが家庭で出来るようになることもあり、ある程度の効果が予測できる。
また、地味だが進めたいのが自転車道の整備である。
● カーシェアリングシステム
Car-Less化の第2段階として期待しているのが、カーシェアリングである。人のモビリティをできるだけ変えないまま車を減らそうとすると、カーシェアリングが浮かぶ。自家用車は、ほとんどの時間駐車されており、個人的な経済合理性からも無駄な使い方である。停まっていても駐車場料金等、お金はかかるし、都市のスペースを占有しているだけと言える。複数保有時代になり、その傾向はより顕著になりつつある。IT技術により、予約・配車・走行状況管理・課金などのシステムは格段に進歩すると考えられ、国内外でさまざまな実験が開始されている。
円滑なカーシェアリングのために、借り出し時間をフレキシブルにし、現在のレンタカーに近い,日単位の利用を可能とする。また中心市街地,公共施設,鉄道駅,空港,郊外の住宅地など、デポ(拠点)間はタクシー的に片道でもOKにしたり、予約は携帯端末で直前でOKにするなどのサービス充実が必要である。利用者の環境意識顕示効果をねらい、EVやガス車、燃料電池といった車最先端のエコ&インテリカーを使用することも考えられる。
期待されるカーシェアリングシステムの効果は、エコカーの利用による環境改善、環境意識の向上、不要な駐車場スペースの削減、割高なエコカーの利用促進、総量制約によるピーク平準化などが期待できる。
カーシェアリングシステム実現に向けて、鉄道駅近辺等のデポの場所確保、自家用車やトランジットとの料金整合(基本的に,自家用車>カーシェアリング>トランジットになるように)が課題となる。本気で持続可能性を考えるならば,普通車を保有することは馬を持つことと同じくらいにすべきであり、また、システムが成り立つためには多数の参加者が必要であり、タクシー業界をはじめとする既得権益者への対応も課題となる。
TDMやITSは交通問題を改善する方向性としては間違っていないが,現在考えられている施策だけでは人に優しい、環境に優しい未来像とはいえない。多くのパーク&ライド実験が行われたが、バス利用者が車利用者になるという事態を引き起こした。ITSは基本的に車の利便性をあげるため、環境問題の解決とはならない。TDMの精神とITSの技術を生かしたダイナミックな交通の未来像が必要である。
● 日本の実情に合った交通環境作り
日本ほど鉄道インフラが充実した国はなく、鉄道駅を生かした中心市街地の活性化と郊外部再開発で、元祖TODとしての面目躍如をしていきたい。また、都心部における土地利用の純化はまちの魅力を下げる。都心部にも職住近接とにぎわいづくりを。交通料金のグリーン化で,土地利用変化の誘導を図り、トランジット料金の公的補助への道を探る。
幹線道路インフラがかなり充実してきた今、住区や都心部の「交通静穏化」に本気で取り組むべきである。交通問題のまちづくりへの重要性を認識し,行政も縄張り意識を捨て,市民が積極的に関与する交通計画フォーラムを形成し、日本のCar
TechnologyとITを活かした新しい車共存型社会へと進むべきである。
そこで自動車関連産業のメッカである愛知県、また、都心部に十分な道路インフラを持つ名古屋市では未来型交通のショーケースを目指してはどうか。交通関連のビッグプロジェクトとしての中部国際空港,第2東名名神,中央リニア新幹線等、ITS関連のビッグイベントとしての2004年世界ITS会議、また2005年日本国際博覧会を控え、今こそ、交通を中心としたまちづくりを図る大きなチャンスである。
(文責:竹内郁/(株)都市研究所スペーシア)
▲総会議事録に戻る▲
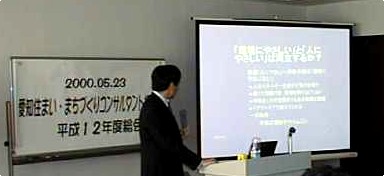 通常、「人にやさしい」移動手段は「環境にやさしくない」といえる。障害者や高齢者など全ての人にやさしいためには、①人のエネルギーを使わず動力を使い、②座って移動でき,荷物も持たなくてよい、③雨風をしのぎ空調までもある快適な空間(箱)、さらには④ドアツードアで運んでくれることが求められる。これで行くとその移動手段は、自動車を指し、究極は運転手付リムジンとなる。
通常、「人にやさしい」移動手段は「環境にやさしくない」といえる。障害者や高齢者など全ての人にやさしいためには、①人のエネルギーを使わず動力を使い、②座って移動でき,荷物も持たなくてよい、③雨風をしのぎ空調までもある快適な空間(箱)、さらには④ドアツードアで運んでくれることが求められる。これで行くとその移動手段は、自動車を指し、究極は運転手付リムジンとなる。 Car-Dependentな街の対極として、全く車を必要としないCar-Freeな街が考えられるが、ここまで依存してしまった以上、突然の変化は不可能であり、「軟着陸」を検討したい。散歩・ドライブなどは別として交通には必ず何らかの目的行動が存在する。つまり、交通問題は交通対策だけでは解決できず、土地利用やライフスタイルの変化との連動が重要である。職住近接の土地利用や、銀行などのサービス機関のオンライン化、あるいは週5日の通勤体制を4日にするなどの施策が考えられる。
Car-Dependentな街の対極として、全く車を必要としないCar-Freeな街が考えられるが、ここまで依存してしまった以上、突然の変化は不可能であり、「軟着陸」を検討したい。散歩・ドライブなどは別として交通には必ず何らかの目的行動が存在する。つまり、交通問題は交通対策だけでは解決できず、土地利用やライフスタイルの変化との連動が重要である。職住近接の土地利用や、銀行などのサービス機関のオンライン化、あるいは週5日の通勤体制を4日にするなどの施策が考えられる。